![]() �Êy�b�c�ЂƂ育��
�Êy�b�c�ЂƂ育��
�@���̑�D���ȌÊy�̂b�c�̒�����A�}�C�i�[�Ȃb�c��ŐV�b�c�ɂ��Ă��Љ�悤�Ǝv���܂��B�Êy�̂��炵���i���܂��傤�B
�`�g�i99/03/23�j
��֘A�b�c�i�Êy�n�j�G�k�R�[�i�[��
AFFETTI MUSICALI (�u�m�F�Ԓ������A�q�����FALEJANDRO MOGUILLANSKY�AVC�FJOB�@TER HAAR�ACEM�FCARMEN LEONI) �@�u�֘A�b�c�R�[�i�[�v���I�̂Ƃ��Ă����}�C�i�[�b�c�B�c�O�Ȃ�����{�����ł͎�ɓ���܂���B�`�g�̎����Ă���̂͐ԒÂ���A���N�̂Q���ɂ��̒c�̂������������s�����Ƃ��ɍw���������́i���̎��̗l�q���������ցj�B�����ǂ����Ă��Ƃ���������������Ⴂ�܂�����A�`�g�܂Ń��[�����������B�ԒÂ���ɘb���Ă݂܂��傤�B����̗������Ɏ����Ă��Ă���邩������܂���B �@����͂����ƁA���̒c�́B�܂��͂��̑����ЂԂ�ɋ�������܂��B�ԒÂ���͓��{�l�B���R�[�_�[�̓A���[���`���A�`�F���̓I�����_�l�A�`�F���o���̓C�^���A�l�ƑS���������̈Ⴄ�l�������W�܂��Ă��܂��B�ԒÂ���͂��̂ق��u�I�[�P�X�g���E���@�b�Z�i�[���v�Ƃ�����͂���̑����Ђ̃I�P�𗦂��Ă��܂��i������̂b�c�͗��N�S�����a�h�r���甭���\��I�j�B�ԒÂ���́A���w����Ƀ��R�[�_�[��MOGUILLANSKY����Əo��A����Ȃɂ��������R�[�_�[�t�҂������̂��Ƒ�ςȃV���b�N�����悤�ł��B����ȗ��A���̃A���T���u���ŋ������Ă��܂��B �@�����ŏ��ɂ��̉��t�����̂́A���͐ԒÂ��^�]����Ԃ̒��B�ނ̉��t��̎�`�������Ă��ă`�F���o�����^��ɁA���̉Ƃɑ����Ă��炤�r���ł����B���̂���͂܂��b�c�ɂȂ�O�B�J�Z�b�g�e�[�v�ł��B���łɖ���x���A���������̂ł����A���̉��t�����r�[�ɃV���b�N�̂��܂肷������ڂ����߂Ă��܂��܂����B����ȃe���}�������̒��ɂ���B����Ȃɖ��킢�[�����@�C�I�������A����Ȃɔ��������R�[�_�[���E�E�E�B�������t���Ă��������̋Ȃ��A�S���ʂ̋ȁA����S���ʂ̐��E�̂��Ƃ̗l�ɂ������Ă���̂ł�����B���{�l��O�ɂ͂��Ⴎ�̂����Ȃ̂ŁA������}����̂ɕK���ł����B �@���t�́A����h���I�ŃG�l���M�b�V���A�������ߓx�������Ď���Ȃ��ƂĂ����炵�����t�ł��B�ߔN�e���}���Ƃ����A�h���I�Ȃ����ʼn��i�ȉ��t�������̂ł����A���̉��t�͎h���I�ł���Ȃ���ǂ����C�i�ɂ��ӂ�Ă��܂��B���̖̐̂��ՁA�u�����b�w���A�N�C�P���A�r���X�}�A���I���n���g�̃g���I�\�i�^�W�ɂ���������炸�B�����āA�����ɂ������I�ȑ����Ƃ��݂��̌��̒ʂ����|�������B�e���}���̃A���T���u���̊y�������\�������킹�Ă���܂��B�������Êy������t����A�}�`���A�ɂ��A������x�����̃��p�[�g���[�����グ�Ă݂����Ǝv�킹��悤�Ȃ���ȉ��t�ł�����܂��B�l�X�Ȗ��͂����Ղ�̂b�c�ł����A�Ȃ��ł��ԒÂ���̂u�m���ō��ł��ˁi���{�l�́u���@�C�I���������Ȃ���������ǁv�Ȃ�Č������Ă��邯�ǁA����͑S���̋t�ł��j�B�e���}���̃��@�C�I�����E�\�i�^������Ȃɂ����Ȃ��Ƃ͎v���܂���ł����B�ʑt�ቹ���Ȃ��Ȃ������ł����ł��B �@�ŋ߁A�v���̉��t�Ńe���}���̃g���I�\�i�^���@��قƂ�ǂȂ��Ȃ�܂����B�܂��āA���@�C�I��������݂̂͊F���ɓ������B���ꂾ���ɁA�ނ�̍ė�������҂������B�����āA���̂b�c�����{�ł�葽���̐l�����ɂ������悤�ɂȂ��Ăق����B����ȋC�����܂��B�ƊE�ʂ̕��c����A���Ƃ��Ȃ�܂��H TELEMANN �uTRIO&SOLO SONATAS�v�iEMERGO EC3952-2�j �g���I�E�\�i�^�j�Z���A�C�Z���A�֒����A�C�Z�� ���@�C�I�����\�i�^�@�C�����A�`�F���\�i�^�@�j�����A���R�[�_�[�\�i�^�@�֒��� �`�F���o���̂��߂̑g�ȃg�Z��
�i98/12/06�j
|
�@�P�P���Ƀv���K���f�B�G���Ƌ��ɂa�b�i�����ق���������`�D�V���^�C�A�[�̗����L�O�ՁB�P�Q���Q�A�R���̋ߍ]�y���o���b�N�V���[�Y�u�o�b�n�E�g�����X�N���v�V�����@at �����I�y���V�e�B�ߍ]�y���v�̉��t�Ȗڂ��ꑫ�����������Ƃ��ł��܂��B�����t���@�C�I�����\�i�^��Q�ԁA��R�Ԃ̃o�b�n���g�ɂ��ҋ��̂ق��AJ.A.���C���P���́u�z���g�D�X�E���W�N�X�v�Ƃ����ȏW�̕ҋȂ����^����Ă��܂��B�����t���@�C�I�����\�i�^�Ƃ����A���@�C�I�����Ƃ����ʏ�͒P��̐����������t���邱�Ƃ��Ȃ������y��P���ŁA�t�[�K���͂��߂Ƃ��镡�G�ȃ|���t�H�j�[�����t������ȂƂ������ƂŒm���Ă��܂��B�������A�����Ȃ閼��������Ă��Ă��A���Պy��̂悤�Ȃ킯�ɂ͍s���܂���B�����ŁA�o�b�n�́A���ۂɂ͒e���Ă��Ȃ����ł����������e���Ă��邩�̂��Ƃ���������悤�ɐ����̓������H�v���Ă��܂��B���Պy��Ȃ�Γ��R�e���ł��낤�����u�Î��v���Ă���̂ł��B�����āA���t�Ƃ����������u�Î��v���ꂽ���A�a���̋����������Ȃ��牉�t���Ă���̂ł��B�ł�����A�u�����炯�v�̊y���ł��A�����ȃt�[�K�̂悤�ɕ�������̂ł��B���������O�͂��������u�Î��v���ꂽ�����������B���ꂪ���̋Ȃ��ЂƂ̑�햡�ł�����܂��B���������u�Î��v�����ۂɉ��ɂ��Ă݂�Ƃǂ��Ȃ邩�B���̓��������� �u�ҋȏW�v�ɂ�����Ă���̂ł��B���āA���̂b�c���Ă݂ċ����̂́A��͂肻�̋����̖L�����A�₩���ł��B�����āA�o�b�n�͂���Ȃɂ������̉����u�Î��v���Ă����̂��Ƃ������Ƃł��B �@�����悤�Ȃb�c�̓��I���n���g���^�����Ă��܂����A����̃V���^�C�A�[�Ղ́A����ɕ�������炸�̂������肵�����h�ȉ��t�ł��B�����Ċ���Ă�킸�A���̑�Ȃɐ��ʂ�����g��ł��܂��B���X�Ƃ��Ă��Ȃ��猈���ďd���Ȃ炸�A���̐����������Ɖ��t���Ă��܂��B�ߍ]�y���ł͎��_�˗����u�����t�v�S�ȉ��t����J���Ă��܂����A���̎��Ƃ͈ꖡ������u�����t�v�̐��E�����\�ł���ɈႢ����܂���B �o�b�n�ҋȂɂ��`�F���o���\�i�^�W�iSONATE PER IL CEMBALO) �@TELDEC 3984-21461-2(�A���Ձj�����Ղ̓��[�i�[�~���[�W�b�N����܂��Ȃ������I BWV.964-966,968,954 �`�F���o���F�A���h���A�X�E�V���^�C�A�[
�i98/10/17�j
|
�@��R�S�������t��ł̃f�r���[�ła�b�i�����o�[�������^���ꂽ�u���Ƃ��̃��r���i�u���Ƃ��́v���Ђ炪�ȕ\�L�ɂ����܂����j�v�B�����͋v�X�Ƀ��r���̂b�c���Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă������ɁA���c����P���̂b�c��n����܂����B�W���P�b�g�ɂ͂��̗L�����u���i���U�v�̊G�B���ɏ����Ă���o���҂�������Ȃ�Ƃ����ɂ��uRobin Blaze�v�̖��O���I�@�`�g���������茩�����Ă����̂ł����A�����������ɂȂ��Ă����̂ł��ˁB���́A���̂b�c�����A�a�b�i��R�S�������t��̃v���O�����Ɍf�ڂ���Ă����u���r���E�u���C�Y�@�C���^�����[�v�̒��ŁA�a�b�i�����h�����݈����㓡�ؕ�q�������Љ�Ă�����̂������̂ł��B�C���^�����[�̂��Ƃɂ��̂b�c�ʼn��t����Ă���ȂŒ����������ł��B �@�㓡����ɂ��A���̂b�c�́A�_����B���`���u���i���U�v�̏ё����`���������A�|�[�Y���Ƃ郂�i���U�́u���݁v���₳�ʂ悤�y�m�������ق��A�@�����Ƃ����Ƃ��������̋L�q�ɑz�����̂ŁA���̓����̐����̋ȁA��y�Ȃ���\������Ă��邻���ł��i����ɂ����̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���܂����j�B�ł��A�b�c�Ɏ��^����Ă���Ȃ́A�����Ĕ��܂����Ȃ���ł͂Ȃ����A���\�������܂����Ȃ�����B�I�[�{�G�̑O�g�V���[����o�O�p�C�v�̂悤�Ȃ������܂����y����g���Ă������ŁA���B�I�[���ɂ��߂����ȋȂ�����B�����������Ƃ����������̂ł��傤�B���i���U�̃��f�����āA����ȋȂ��āA����Ȕ����ׂ�Ȃ�āA�`�g�̂悤�Ȗ}�l�ɂ͗������o���܂���B �@���āA�̐S�̃��r���ł����A���܂Œ����Ă����̂��o���b�N���S�ł����������ɁA����̃��l�T���X���̂ɂ͂��Ȃ�قȂ��ۂ��܂����B���̓������A�\���͂͑��ς�炸�Ȃ̂ł����A����̂́u�F�C�v������B�����A�㓡������w�E���Ă���悤�ɁA�����Ɏv����������߂邠�܂�A���ꂪ����ꂻ���ɂȂ�A�܂�A���X�o���b�N�I�ȉ̂����ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��c�O�ł͂���܂��B�������A���Ƃ��Ƃ͐��̑��̏o�g������A���������W�������͖{���I�ɂ̓��r���ɂ͂����Ă���悤�ȋC�����܂��B �@����ɂ��Ă��A�Q�O�N�قǂ̃��l�T���X���̂̉��t�ƌ����A�܂�Łu�����̂Ȃ��v�N�����z������V���[���A�c�B���N�����i�ɂ������܂����邢���ɂ��e��ȉ��t�����������̂ł����A���̃R���R���f�B�A�̉��t�́A����ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ��������Ă���ȂƂ�����ۂ��܂����B����ȒP���Ȋy��ł��������ł����Ԃ�ς����̂��ƁA���l�T���X�y��̕\���͂��ĕ]�����܂����B �@���̂b�c�́A�V�������n���J���A���悢��J�E���^�[�e�i�[�E�̃X�^�[�̍����ˎ~�߂�܂łɂ����������r���́A���͂���P���ɂȂ邱�Ƃł��傤�B �u���i���U�̂��߂̉��y(Music for Mona Lisa)�v(METRONOME MET CD 1023)�A���Ղ̂� �J�E���^�[�e�i�[�F���r���E�u���C�Y�AMark Levy�w��Concordia |
�@���ɂb�c���u�����̃��r���v���r���E�u���C�Y�ƃC�M���X�J�E���^�[�e�i�[�E�̑��l���W�F�[���Y�E�{�E�}���̖��̃f���G�b�g���������܂����B�uLO SPOSALIZIO�`The Wedding of Venice to the Sea�v�i�������j�Ƃ����b�c�ŁA�P�V���I�͂��߂̃��F�l�`�A�ł̏��V�Ղ̋V���ł���u���F�l�`�A�ƃA�h���A�C�Ƃ́v�����������y�ōČ������Ƃ������̂ł��B�Q���g�݂ōŏ��͌����s��A�Q���ڂ̓~�T�Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂��B�P�V���I�����̃��F�l�`�A�Ƃ����A�W�����@���j���A���h���A�E�K�u���G������������B�T���}���R�̏�����n�܂�A���̂ӂ���̍�i�𒆐S�Ƀ����e���F���f�B�Ȃǂ��̎���̒����ȍ�ȉƂ̍�i�������玟�ւƉ��t����A�܂��A�t�@���t�@�[���A�s�i�̃h�������Ȃ�܂��B������A���F�l�`�A�ł��̏��̉������ۂɕ����Ă�������Ȃ̂ŁA�Ȃ��A�ƂĂ��������������Ă��܂��܂��B �@����͂����ƁA���r���ƃ{�E�}���̃f���G�b�g�ł����A�W�����@���j�E�K�u���G���̃}�h���K���uLieto godea sedendo�i���͊y����ō����Ă���i�H�H�j�j�v���̂��Ă��܂��B�������A�f���G�b�g�Ƃ����Ă���̎���Ƃ͈قȂ�A�K�u���G���ɓT�^�I�Ɍ�����Q�d�����̍����������\���ɂȂ��Ă�����̂ł��B������āA�͂����肢���Ă킽���̓{�E�}���̎���͏I������ȂƂ����C�����܂����B��͂�A���̐����Ƃ����͉̂B���Ȃ����̂ł��ˁB�Ȃ�ƂȂ��ꂵ�����ɐ����o���Ă���悤�ɂ������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���̕��A�͂ꂽ���킢�Ƃ����̂�����ɂ͂���̂ł����A�{�E�}���̉̂����Ղ�Ƃ����̂ɂ́A�ǂ����ɂ���Ȃ��ł��B�ǂ����Ă����܂Ŋ����������āH�����A���r���̉̐������܂�ɔ������A����₩�ŁA��X��������B�{�E�}���̉̂́A�܂�ŁA�N�V�����V�k���V���v�w�ɐl���̔߈��ł��Â��Ɍ��|���Ă���悤�Ȋ����B����A���r���́A�����ȉԉł̏����ȋC�����ʼn̂��Ă���悤�ɂ���������B�������ɂ͂ǂ��炪�ӂ��킵�����āH�@�����A��͂�A���r���ł��ˁB �@�q���̎��ɃW�F�[���Y�E�{�E�}���̉̂��Ĉ�����Ƃ������r���B�{�E�}���Ƃ����Ή_�̏�̓���̐l�B���̃{�E�}���ɔF�߂��A���ɂ̓f���G�b�g�܂ʼn̂킹�Ă���������r���B��̂ǂ�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��炱�̉̂��̂����̂ł��傤�B �@������A�s�i����A��y�Ȃ���A�A���A����A��������A�Ɛ��肾������̂��̂b�c�B���܂Ȃ�Q���g�łQ�R�O�O�~�ʂŔ����܂��B���X�Ō������琥���Ă݂Ă��������i�g�l�u�a�J�X���������߂̂悤�ł��j�B �@����ɂ��Ă����r���̘^���y�[�X�͂����ւ�Ȃ��̂ł��ˁB �uLO SPOSALIZIO�`The Wedding of Venice to the Sea�v�ihyperion CDA67048)�Q�����P���͂��܂������̂悤�ł��B R.KING�w��THE KING'S CONSORT J.BOWMAN�AR.BRAZE��
�i98/07/21�j
|
�@�U������V���ɂ����Ă̂a�b�i������t��ŁA���ɓ�̃x�[����E���̂Ă��u�����̃��r���v���r���E�u���C�Y�̂b�c���܂��܂��o�ꂵ�܂����B�����́A����̏@���ȂɃp�[�Z���́u���Z�V���A�̓��̂��߂̃I�[�h�v�̂Q�g�ł��B��������A���̑��o�g�̋��݂������ɔ�������Ă��܂��B�ŋ߂ł͌��ɂP���̃y�[�X�ŐV�������\����郍�r����u���C�Y�B�u�a�b�i�A�����̐V�l���@���H�v�Ȃ�Ďv���Ă������ǁA���łɑ����̔�����q�̂悤�ł��ˁB�a�b�i�Ƃ̏��b�c�������ɂȂ邱��܂łɂ́A���Ȃ�̐��̂b�c���V���b�v���ɂ��킵�Ă��邱�Ƃł��傤�B�i98/07/10�j |
| �s�D�g�D�e�D�j�����������u�}�^�C���ȁv�i�m���E�F�[AURORA�@ACD
4994) �@�ŏ��ɂ��Љ��̂́A�m���E�F�[�̍�ȉƂs�D�g�D�e�D�j�����������i�P�X�S�T�N���܂�j�́u�}�^�C���ȁv�ł��B���̋Ȃ́A�O���S���I���̂���V���b�c������܂łɂ�����`���I����y�̗l������肢��Ȃ�����A��_�ȕs���a���ȂǁA���㉹�y�I�ȗv�f���������A�E�J�y���̍�i�ł��B�o�b�n�́u�}�^�C���ȁv�������ł����A���ʂ̓G���@���Q���X�g�ɂ��Ă��C�G�X�ɂ��Ă��A�\�����A�܂��͒P�ꐺ���̍����ʼn̂��邱�Ƃ������̂ł����A���̍�i�͂������̍����̏W�܂�ŁA���ꂼ��̍��������̂��̂��̖�����^�����Ă��܂��B���̒��ŁA���r����u���C�Y�́A�C�G�X�̃p�[�g���̂��e�p�[�g��l���̍������̍ŏ㐺���i�������J�E���^�[�e�i�[�j��S�����A���̓��������ӂ�鐺�Ŗ��������Ă���܂��B�Â��X�^�C���Ɍ���̐��_���h�����@�����y�Ƃ����A�`�D�y���g�����ɗL���ł����A����ƂȂ�ƂȂ����Ă�����̂́A��_���ł͂��̍�i�̕����͂邩�ɏ����Ă��܂��B�ł�����A�u�S�̈��炬�v�Ƃ��������͒����Ă��Ă��܂肵�Ȃ���������܂���B�������A�C�G�X�̋�Y�Ƃ��A��q��Q�O�̐S�̊����Ȃǂ͂�苭����ۂÂ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�� �X��������͂��܂����A�A�E�J�y���ł̃��r���̖��͂�m�肽���l�ɂ͂������߂ł��B���̉̎肽�����C�M���X���𒆐S�ɁA�Êy�̐��E�ł��Ȃ��݂̖��̎肪�����Q�����Ă��܂��B �s�D�g�D�e�D�j�����������u�}�^�C���ȁv �w���F�s�D�j�������@�I�X���J�e�h���������c �\���X�g�F�q�D�a���������C�h�D�o�����������������C�i�D�b���������������� �i�H�t���Ίۓd�C�œ���j |
| �g�D�p�[�Z���u���Z�V���A�̓��̂��߂̃I�[�h�v�i�n�����j�A�����f�B�t�����X�@HMC901643) �@��������p�[�Z���̗L�����u���Z�V���A�̓��̂��߂̃I�[�h�v�B�w���͂�����݂��oh.�w�����F�b�w�B�����炭�A���r���ƃw�����F�b�w�̑g�ݍ��킹�ł̍ŏ��̂b�c�ł��傤�B�w�����F�b�w�Ƃ����A�`�D�V�����Ƃ̃o�b�n�̃J���^�[�^���͂��߂Ƃ��鐔�X�̋������m���Ă��܂����A����̓C�M���X���̂Ƃ������ƂŁA���r�����g�����̂ł��傤���H�@�w�����F�b�w�܂ł��g�����炢������A���r���͂��łɃ��[���b�p�ł͊��S�Ɉꗬ�̎�̒��ԓ�������Ă���Ƃ����؋��B�a�b�i�t�@���Ƃ��ẮA�w�����F�b�w�ɐ���z����Ă��܂����̂͂�����Ɖ��������ǁA���r�������ꂾ�������̎肾�Ƃ������Ƃ����A�o�b�n�̂b�c�Ƃ��Ă͂a�b�i���ŏ��ɂȂ�ł��傤����A����ł悵�Ƃ��܂��傤�B���r���̏o�Ԃ̓\���͏��Ȃ��A�f���G�b�g�������ł��B�o�X�A�A���g�A�e�m�[���Ƃ̃f���G�b�g������̂ł����A���肪�ǂ̐���ł����Ă��A�ƂĂ��ǂ����a���Ƃ�Ă��āA���������Ƃ������Ȃ������ۂ��\�������Ă��܂��B��͂�A���̑��o�g�Ƃ������ƂŁA�A���T���u���ɂȂ�Ɣ��Q�ł��ˁB���������A����̗�ؔ��o������Ƃ̃f���G�b�g���Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B�� �r���̉̂��āA�{���ɗ݂͂��Ȃ��Ď��R�B�����āA���������܂������Ȃ��B�ł��A�S�ɂ��݂����Ă����ł��ˁB����̓C�M���X�̐��̑��o�g�ґS�̂Ɍ����邱�Ƃł����A���̈���ŁA���̑���Ȃ������������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���r���̏ꍇ�ɂ͕\���́A�����͂�����̂ŁA������Ȃ��������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B��قǓ���ȉ̂͂킩��܂��B �@���Łi�Ƃ����Ă͂Ȃ�ł����j�ɍ����ł����A�����̂悤�Ƀ��B�u���[�g���������������łӂ��݂̂��鐺�B�����ȉ����B�����A�����̃o�b�n�ɔ�ׂ�Ƃ�≸�₩�B�Ȃ̐��i�f���Ă���̂ł��傤���ǁB�C�M���X�l�̃p�[�Z���Ȃ班�N�������g�����Ƃ��������A����͂���Ō��\�������ǁi�l�I�ɂ͋C�ɓ����Ă��܂��j�A����������l�̊����ȃA���T���u���Ƃ����̂����܂ɂ͂������Ȃ��Č��������ł��B �@�Ȃ��A���̂b�c�ɂ̓I�[�{�G���s�`�j�`�@�j�h�s�`�y�`�s�n������o�����Ă��܂��B �g�D�p�[�Z���u���Z�V���A�̓��̂��߂̃I�[�h�v �w���F�o���D�w�����F�b�w�@�^�R���M�E���E���H�J�[�� �\���X�g�F�r�D�g���������������A�q�D�a���������A�l�D�o�������������C�i�D�`������������ |
�u�m�F���_�ˁ@���A�t�H���e�s�A�m�FBOYAN VODENITCHAROV(DENON Aliare COCO-80851������) �@���_�˗����������悢��x�[�g�[���F���̃��@�C�I�����\�i�^�ɒ���B����܂Ń��[�c�@���g�A�n�C�h���Ȃǂ̑����̂b�c�ł͍D�]���Ă��܂������A�x�[�g�[���F���́A������Љ���s�A�m�g���I�W�ɑ���2���ځB�x�[�g�[���F���̃I�[�P�X�g���ȁA���t�ȁA�����y�ȂȂǂł͂��Ȃ�ȑO����Êy��̉��t���s���Ă������̂́A���@�C�I�����\�i�^�̉��t�Ƃ����̂͂܂��܂����Ȃ��悤�ł��B���[�c�@���g�͌��\�����Ă�����ł����B�Ƃ����̂��A���[�c�@���g�̎���̉��y�Ȃ�A�o���b�N���̊y���t�@�ł�����x���t�ł���̂ł����A�x�[�g�[���F���ȍ~�ɂȂ�ƁA�u�o���b�N���v�ʼn��t�����̂ł͂��͂�u�I���W�i���v�Ƃ͌����Ȃ����炢�A���y�̓��e�ʂł��y��̐��\�ʂł��傢�ɕς���Ă��Ă��܂��Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��͂�|�������������ł͂��߂ŁA�y��̍\���A�����đt�@�ɂ��Ă����̎���ɂ��������̂��g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���C�i�[�m�[�c�ɂ��A���_�˂���͂��̘^���ɓ������āA�����g���Ă���P�U�X�P�N���̃O�����`�[�m�ł͂Ȃ��A�P�V�V�Q�N���̃����h���t�B���g���A�܂��A�o�C���[ �A�N���C�c�F���A���[�h�ȂǁA�x�[�g�[���F���̓�����̋����{���Q�l�ɂ��A�o���b�N�����t���鎞�Ƃ͈�����t�@�i�y��Ɋ{���悹�Ă������j�ʼn��t���������ł��B �@���t�ł����A�S�̓I����ςɃe���V�����������A�����ɂ������ė͋����ɂ�������炸�A�_�炩���ʂ����A���ɑ��ʂȉ��F����g�����A�ω��ɕx���t�ł��B���t�̃e���V�����͍����Ă��A������ɉߓx�ْ̋���^���Ȃ��B�����ƃ����b�N�X����Ƃ��������Ă����Ƃ��낪�t�@���Ƃ��Ă͂����Ȃ��炤�ꂵ���B���ɗL�����u�t�v���D�����A�����������A�V���Ȑ����̑����ƂƂ��ɁA�C�܂���Ȃ��̋G�߂̋C���t�ɂ悭������Ă��܂��B�s�A�m��VODENITCHAROV�i���H�f�j�`�����t�j���A���_�˂���ɕ�������炸��ςɗ͋����A�^�b�`���������肵�Ă��邹�������̉��̗����n�b�L���Ƃ킩��A����ł��Ȃ��特�Ɖ��̂Ȃ��肪���ɃX���[�Y�B���݂��Ɂu���t�v������Ƃ����Ĉ���I�Ɉ�������ł��܂��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���ꂼ��̖�����F�����咣�͖��m�B�������A�����͌Êy��B���F�̐e�a���i�܂��͗n�������j�ɂ���āA�����āu�Η��v�Ƃ��������͂��܂���B�����āu�Êy�큁�n��v�ȂǂƂ����C���[�W�́A���̉��t�̂ǂ�����������������Ƃ͂ł��܂���B�s �A�m�g���I�ɑ������̂b�c�̓x�[�g�[���F���̉��t�j�ɐV���Ȉ�y�[�W���L�����̂ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B���̂b�c�̑��҂���҂������Ǝv���܂��B ���^�Ȗ� �x�[�g�[���F���^���@�C�I�����\�i�^��P�ԁA��R�ԁA��T�ԁu�t�v
�i98/06/24�j
|
LES PRETENTIONS DU VIOLONCELLE�i���`�F���J�[��RIC 114120) �`�F���F��؏G���� �@�u���B�I�����`�F���̖�]�v�@�ߌ��ȃ^�C�g���̂��̂b�c�́A�P�W���I�͂��߂��璆���ɂ����Ẵt�����X�ɂ�����`�F���̂��߂̍�i���W�߂����́B�o���Ղ��u���B�I�����i���@�C�I�����j�̖u���v�u���B�I�[���̗i��v�Ƃ������̂�����܂��B���������P�V���I�A���z�����C�P�S���̋{��ł́A�M���̊y��Ƃ��ă��B�I�[���i���B�I���E�_�E�K���o�j�����Ă͂₳��Ă��܂����B�f��u�߂��肠�����v�ŗL���ɂȂ����T���g�E�R�����u�A�}�����E�}���A�A���g���[�k�E�t�H���N���Ȃǂ̖��茓��ȉƂ����X�Ƃ�����A�D��ł��͋�����i�ݏo���Ă��܂����B����A�P�V���I�I��肱��ɂȂ�ƁA���׃C�^���A���烔�@�C�I�������̊y�킪�`���A�₪�ċ{��⌀��ł��g����悤�ɂȂ�܂��B�C�^���A�l�������ɂ���āA���C�P�S�����C�ɓ���̃I�y���ɂ����@�C�I���������I�[�P�X�g���y��Ƃ��ēo�ꂵ�܂��B�����āA����Ƌ��ɁA�C�^���A���A�����R�������̉e��������i�������������悤�ɂȂ�܂��B�����A���������@�C�I�������͂����܂ł��V�Q�� �̖�Ȋy���B���l�̗x��̔��t�y��ŁA�{��ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��B��͂�A���̈Ќ��������y��̓��B�I�[���ł����Ƃ����Ă��܂����B�������A���̂����A���@�C�I�������͂܂������܂ɋ{��ɂ��L����A�u��̓����v�Ƃ����X���[�K���̂��Ƃ��u�C�^���A�̌`�����t�����X�̓��e�Ŗ������v�悤�ȃC�^���A���̋Ȃ��N�[�v�����Ȃǂɂ���đ����������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�P�W���I�A���C�P�T���̎���ɂȂ�ƁA���S�Ƀ��@�C�I�����𒆐S�Ƃ����C�^���A��̍�i���嗬�ɂȂ��Ă��܂����B���N���[���A�M�j�������͂��߂Ƃ��鍡���ł��L���ȍ�ȉƂ������ă��@�C�I�����̂��߂̍�i�������悤�ɂȂ�܂����B����A����ɔ����������B�I�[���x���҂��������B�I�[���i��̉^�����n�߂܂����i���̂R���̂b�c�̃^�C�g���̗R���ł��郋�E�u�����́u���B�I�[���i��_�i1740�N�j�v���L���j�B����Ȏ���ɁA���B�I�[�����{��̎������������艺�낷�ׂ��o�ꂵ���̂����@�C�I�������̃`�F���B�����āA������������w�i�������Ƃ����f������i���W�߂��̂������u���B�I�����`�F���̖�]�v�Ȃ킯�ł��B �@�`�F���������y��Ƃ��Ă̒n�ʂ�^������悤�ɂȂ����̂́A���قnjÂ��b�ł͂Ȃ��A�P�V���I���Ή߂��ɂ悤�₭�C�^���A�ł킸���ɍ�Ȃ����悤�ɂȂ����Ƃ̂��ƁB�o�b�n�́u�����t�v���`�F�����y�̗��j�̒��ł��������̂��̂Ƃ����Ă������قǂł��B���ꂪ�킸���T�O�N�Ń��B�I�[����ǂ����Ƃ��Ă��܂����̂ł��B�����Ŏ��グ���Ă���R���b�g�A�{�A�����e�B�G�Ȃǂ���i�������Ă��܂��B�L�����u��ؐl�̃G�A�v�����^����Ă��܂��B�����ł��߂����ɉ��t�����@��Ȃ��Ȃł����A�����炭�����̃t�����X�ł͂��Ȃ�̏Ռ���^�������̂Ǝv���܂��B �@�G������́A�����I�P�Ȃǂŋ������Ă��钇�Ԃ̃`�F���X�g���W�߂āA���̂Ȃ�Ƃ��������Ґ��̋Ȃ����ɂ��̂����ɐ��������Ɖ��t���Ă��܂��B18���I�t�����X�̃`�F�����y�̗��j��m���ŁA�꒮�̉��l�����肻���ł��B
(98/06/16)
|
�@���{���ėǂ��a�b�i�́u�o���b�N�E�A���A�W�i�V��̐��j�v���������ꂽ�̂Ɠ�������A�C�̌������ł́A���J�E���^�[�e�i�[�̑��l���A���h���A�E�V�����̃o�b�n�u�A���g�̂��߂̃J���^�[�^�W�v�������ɂȂ�܂����B�V�����Ƃ����A�u99�N�x�ɂ͂a�b�i�o�ꂩ�H�v�Ƃ����Ă��܂����A�ėǂ���̃��C�o���Ƃ����ׂ��A���܂��Ԓ��������Ƃ������̎�ŁA��N���̂m�g�j�@FM�u���̃o���b�N�v�ŁA�ėǂ��ނɂ��Č���Ă����̂���ۓI�ł��B�f��u�X�[�p�[�}���v�̎�l���ɂȂ�ƂȂ����e�����Ă��āA�̎����߂Ă��f��X�^�[�Ƃ��Đ����Ă�����̂ł͂Ǝv����قǒ��g�Ńn���T���B����ȃV�������A�o�b�n�̃\���J���^�[�^�R�ȁi�R�T,�T�S�C�P�V�O�ԁj��^���B�T�S�ԂƂ����A�ėǂ���̂b�c�ɂ����^����Ă���A���g�̂��߂̃\���J���^�[�^�̑�\�i�ŁA���܂܂Ŏ��ɑ����̃J�E���^�[�e�i�[�̎肪���R�[�f�B���O���Ă��܂��B���҂���ׂĂ݂�ƁA�ėǂ���ƃV�����̈Ⴂ�A�����āA�w���҂ɂ����߂̈Ⴂ���������đ�ςɖʔ����ł��B�Ƃɂ��� �A�a�b�i�̉��߂������Ɍ��I�ň�ې[�����A�ėǂ���̉̂������ɖ��킢�[���������߂Ċ����܂��i���͂�͂�a�b�i�̕����D���ł��j�B�V�����̓V�����ňꌾ�ꌾ����������ƁA������߂ė͋����̂��グ��B��͂�A���炵���̂͑�R�T�ԁB�a�b�i�ł����x�����グ��ꂽ�A�I���K���\��������Ȃł��B�a�b�i�̘^���ł͕ėǂ���Œ�����Ǝv���Ă����̂��A�ʖڂɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�����ɒN���̂��̂����C�ɂȂ�Ƃ���ł����A�u�L�͌��v�V���������̂b�c�������ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�a�b�i�ł͉̂�Ȃ���������܂���B�R�[�C�̂悤�ɂ��낢��Ȓc�̂Ɠ����Ȃ�^�����邱�Ƃ�����̂Ő�Ζ����Ƃ͂����܂��A���r���E�u���C�Y�����邵�A���[�k�Ȃnj��ɂȂ肤��̂ŁA�ʂ��Ăǂ��Ȃ�̂ł��傤�B��D���ȋȂ����ɏ����ł����͓I�ȉ̂������ł��ˁB �@�I�P�͍��N�̏H�A�k�Ƃ҂����ۉ��y�Ղ̂��߂ɗ�������w�����F�b�w�w���R���M�E���E���H�J�[���B�R���T�[�g�}�X�^�[�����_�˂����A�I�[�{�G���|���Z�[�����k�������Ƃ��������̃R���r�B�u���Ȃ߁v���a�b�i�Ɠ���������A�T�E���h�����Ă��邩�Ƃ����ƁA���ꂪ�ӊO�ƈႢ�܂��ˁB�a�b�i�ł̉��t�̕����A��肠�������݂Ɖ̐S�������܂��B�u�炵���v���悭�o�Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B �@���āA���̂b�c�ɂ́u���܂��v�����Ă��܂��B�u�V�����̃|�[�g���[�g�v�Ɩ��ł��ꂽ���̂b�c�ɂ́A�t�����X�E�n�����j�A�E�����f�B�ɘ^�����ꂽ�ނ̃\���Ȃ����^����Ă��܂��B�o�b�n�́u���Z���~�T�v�u�N���X�}�X�I���g���I�v�A�w���f���́u���T�C�A�v�Ȃǂ̃A���A���V�Ȏ��^����Ă��܂��B�V�����̖��͂�m���ł͈꒮�̉��l�����肻���ł��B �@�ȏ�A�u�֘A�b�c�v�Ƃ����ɂ͏��X�C��������������܂��A���_�˂����^�J������o�Ă���Ƃ������ƂŁA�Љ���Ă��������܂����B �i.�r.�o�b�n�u�A���g�̂��߂̃J���^�[�^�W�v�b�s�F�A���h���A�E�V�����@�w�����F�b�w�w���R���M�E���E���H�J�[���E�I�[�P�X�g�� (���n�����j�A�E�����f�BHMC�@901644)
(98/06/11)
|
�@�Q�����u�x�[�g�[���F���^�`�F���\�i�^�W�v�����A�D�]������؏G�������ƁA�������u���E�̃R���T�[�g�}�X�^�[�v���_�˗������A�����ăn�[�O�ł̓����A�s�A�m��Bart van Oort�������������o�[�ɂ��x�[�g�[���F���A�t�������̃s�A�m�\�i�^�W�B�����m��Ȃ��悤�Ȓ��}�C�i�[���[�x������Ƃ������ƂŁA���͍�N���ɔ�������Ă����̂ł����A�����ɂ��S���C�Â��܂���ł����B�������A���t�͂�͂�ꋉ�i�B���W���[���[�x������o���Ă��\���悭���ꂻ���Ȃقǂł��B�A���T���u���������҂����荇���āA�܂��A�x�[�g�[���F���ɂ��肪���ȁu�͂̓������v���t�ł͂Ȃ��A���̗͂��������A�����Ă��ĂƂĂ������b�N�X�ł��鉉�t�ł��B�����Ă���ł��Ă��݂��݂Ɩ��킢�[���B�R���̏G������̃R���T�[�g�ł̉��t���v���o���Ă��܂��܂����B�Ƃɂ����A�������߂̉��t�ł��B �@���āA��؏G�����x�[�g�[���F���̃`�F���\�i�^�S�Ș^����i�s���̂��Ƃ͂����m�ł��傤���A���x�����_�˗����A�x�[�g�[���F���̃��@�C�I�����\�i�^�ɒ�������悤�ł��B��������ƂĂ��y���݂ł��B �u�x�[�g�[���F���A�t�������s�A�m�\�i�^�W�v���_�˗��A��؏G���ABart van Oort �iMasterTone 0107(COLUMNS CLASSICS)) �x�[�g�[���F���^�s�A�m�g���I�σz������i�P-�P�A�t�������^�s�A�m�g���I�σz������i�P�Q���X�U (98/06/06) |
�@�C�M���X�ōŋ��Ԋۋ}�㏸�Ƃ̏��������Ă����u�����̃��r���vRobin Blaze�̂b�c���܂��܂��o�܂����B�u�Z���g�E�|�[���吹���̉��y(Music for St..Paul's)�v�Ƃ���CD�ŁA17���I�㔼����18���I���{�܂ł̃Z���g�E�|�[���吹���ʼn��t���ꂽ���Ȃ��A�u�Z���g�E�|�[���吹�������c�v�ƌÊy��I�P�ʼn��t�������̂ł��B�^�����͂������u�Z���g�E�|�[���吹���v�B�o�b�n�ł����u���g�[�}�X����v�ł����̐��̑����g���Ę^�������Ƃ����������ł��傤���B���^�Ȃ��w���f���́u���g���q�g�E�e�E�f�E���v�u���s���[�e�v�A�i�D�u���E�A�v�D�{�C�X�̏@�����ł��B���r���N�́A�J�E���^�[�e�i�[�Ƃ��đ劈��I�@���܂܂ł̂b�c�̒��ł͂�����o�Ԃ������A�ނ̖��͂����\�ł���Ǝv���܂��B�����܂ŗ���ƁA�\���X�g�Ƃ��Ă̎��͂����Ȃ�̂��̂ł��邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B�a�b�i�ł�����w���f�����̂��Ă��炢�����B�w���f���ɂ��u��͂���ꂽ�v�Ƃ��A�a�b�i�����̍������S�̖��Ȃ����Ȃ��炸���邵�A�u���T�C�A�v���肶��Ȃ��āA�����ƃw���f�������グ�āA�����āA���r���N�𑽂��Ɏg���Ăق����ł��ˁB�w���f���������ł����A�u���E�ƃ{�C�X���Ȃ��Ȃ������B�������̂��鐺�Ŏ������������ɔ�������Ă��܂��B�{�C�X�� �Ȃ́A�P�W���I�����Ƃ������Ƃ������āA�I�P�̋����A�a���i�s�A�y����Ƀe�B���p�j�[�̎g�������A�ÓT�h����肵�Ă���悤�ȋC�����܂��B���[�c�@���g�ҋȂ̃w���f���̃I���g���I�i���������͎̂��ۂɐ��Ȃ���܂��j�݂����Ȋ����ł��B �@���̑��ɂ��AR.Blaze���o�ꂷ��b�c�����܂����B������͍�N�����ɂȂ������̂̂悤�ł��B�v�D�{�C�X�iW.Boyce)�̌��ꉹ�y���W�߂����̂ŁA�u�y���E�X�ƃe�g�X�v�Ƃ���1740�N��Ȃ̃}�X�N�i���ʌ��j�̂Ȃ��ň�Ȃ����A���A���̂��Ă��܂��B�V�����b�c���o�ꂷ�邽�тɏo�Ԃ������Ȃ��Ă������r���B���N��ɂ̓C�M���X�̃J�E���^�[�e�i�[�E�̑��l�҂ɂȂ��Ă������Ȑ����ł��B �uMusic for St..Paul's�v�Z���g�E�|�[���吹�������c�AJ.Scott�w��THE PARLEY OF INSTRUMENTS Julia Gooding,Robin Blaze,R.Covey-Crump���ihyperion CDA67009) W.Boyce�uTheatre Music by William Boyce�`Peleus and Thetis�vP.Holman�w��Opera Restor's Julia Gooding,Robin Blaze��(hyperionCDA66935)
�i98/05/3098/05/31���M�j
|
�@����́A���N�̂a�b�i�ɓo��̓�l�̃\�v���m�A�l�D�V���y�[�Q���ƁA���Ȃ��݁@�u�̂��}���A�v�h�D�V���~�b�g�q���[�[���̃\���A���o�������Љ�܂��B�ǂ�����u�a�b�i�v���X�P�v�炵�����}�j�A�b�N�ȍ�ȉƂ̍�i������W�߂��b�c�ł����A�t�@���̕��ɂ͐����Ă��������������̂ł��B�u�}�j�A�b�N�v�Ȃ̂ŁA���R�����Ղ͂łĂ��܂���B������������[�x�b�N�̃}�C�i�[���[�x�����������甭������Ă��܂��B�p��̉̎��͂��Ă��܂����A��͂���{��̂悤�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B�ł��A���t�̈Ӗ��͂킩��Ȃ��Ă��A���\�y���߂�̂ŁA�p�ꂪ���ȕ��i�`�g�������ł����j���ǂ����B���āA�������ł����A�h�C�c�̃o���b�N���y�𒆐S�Ƃ������p�[�g���[���肪���Ă��܂��B�o���҂��n���Ȃ��炻�̕���̃X�y�V�����X�g����ŁA���t�̃��x�����ŋ߂ł͔��ɍ������̂������悤�ł��B�a�b�i�̃Q�X�g�̎肽�����吨�o�����Ă���A����Љ��V���y�[�Q���A�V���~�b�g�q���[�[���̂ق��A�R�[�C�A�t�����}�[�Ȃǂ��łĂ��܂��B����a�b�i�ɓo�ꂷ��ł��낤�̎肽�� �����̃��[�x������\�z���邱�Ƃ��y������������܂���B�Ƃɂ����A�}�C�i�[������Ƃ����Č����āu����Ȃ��v���[�x���ł��B(98/05/24) |
| M�D�V���y�[�Q���@�u���Ɨ܂̂�����
Tra il riso e il pianto�v B.�X�g���b�c�B�iBARBARA.STROZZI)�u�A���A�A�J���^�[�^�����́v M�D�V���y�[�Q���̃v���t�B�[���̒��ł��Љ��Ă����ޏ��̎�Â���c�́A�uEnsemble Incantato�v�̃f�r���[CD�B �@B.�X�g���b�c�B�i1619-1664?�j�́A���F�l�`�A�Ŋ��A����I�ɂ̓����e���F���f�B�̌�̐���ł���A������u�����o���b�N�v����A�`.�X�J�����b�e�B�`���B���@���f�B�ɂ�����u����o���b�N�v���n������������ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ͂����Ă��A���̃X�g���b�c�B����B��ؓ�ł͂����܂���B�܂��A���O����킩��悤�ɁA�����Ƃ��Ă͂����ւ�ɒ�����������ȉƂł��B���̂��߁A�����̏����̎�ɂƂ��Ă̑�ȃ��p�[�g���[�ɂȂ��Ă��܂��B�u�����v�Ƃ�������ɂ͂��������@�ׂŁA�D�����Ȃ��������Ǝv���A���ꂪ�S���Ⴄ��ł��ˁB�ƂĂ���������M�I�ŃG�l���M�b�V���ł��B����ɁA������������Ƌ��܂��Ă��āA�u���͂��������Ȃ����Ȃ��v�Ȃ�Ďv���Ē����Ă���ƁA���������ɗ����܂��B������̏�����Ɓu�A���e�~�W�A�E�W�F���e�B���X�L�v�̓��W���u�|�p�V���v��4�����Ɍf�ڂ���Ă��܂������A�ޏ��̊G�ɒʂ��鐢�E������Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A��x�����Ă݂Ă��������B�����Ƒ傫�ȃV���b�N���邱�Ƃł��傤�B �@���āAM.�V���y�[�Q���̉̂ł����A�Ȃ��Ȃ����ɂȂ��Ȃ����ʂ̎��_�ŕ]������͓̂���̂ł����A���܂��̎�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł��B�u���������̂��D���ȉ̎肾�v�Ƃ������Ƃ��킩�邾���ł��������l����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�X�g���b�c�B�̉̂Ƃ����̂͂ƂĂ��������̂ŁA��ԈႦ��ƂƂ��Ă��u���i�v�ȉ��t�ɂȂ��Ă��܂������ł����A���i�́A��������Ɨ}����Ƃ���͗}���A���i�ɂȂ�̂�h���ł��܂��B�a�b�i�ł́u���T�C�A�v���̂��܂����A�{���̓V���b�c�Ƃ��A�����e���F���f�B�Ƃ��A�������������͂邩�ɖʔ�����Ȃ����Ȃ��B�o�Ă���b�c���A�o�b�n�U��u���J���ȁv�������قƂ�ǔ�r�I�Â����̂��������B���ꂩ�炪�y���݂ł��B �u���Ɨ܂̂����� Tra il riso e il pianto�v B.�X�g���b�c�B�iBARBARA.STROZZI)�u�A���A�A�J���^�[�^�����́v�icpo�@999 533-2�j M.�V���y�[�Q���AEnsemble Incantato |
| I�D�V���~�b�g�q���[�[�� �i�D���[�[���~�����[�@�u�G���~�A�̈��́A�g���I�\�i�^�W�v �����ẮA�a�b�i�ł������肨�Ȃ��݂ɂȂ����A�V���~�b�g�q���[�[���̂b�c�B ������́A���ɐS�������܂鉉�t�ł��B�V���~�b�g�q���[�[���͂S���́u���n�l�v�ł��C�G�X�̎���߂��ރA���A��X�Ɖ̂��グ�A�����̐l�̐S��ł��܂������A���̂b�c���Ă���ƁA���̎��̂��Ƃ�������̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o����Ă��܂��B��ꂽ���A�߂��݂ɂ��ꂽ���A����A���������b�c�ł��B �@���n�l�X�E���[�[���~�����[�i1619-1684)�́A�P�V���I�̃h�C�c���\������ȉƂŁA�C�^���A�Ŕ��W�����o���b�N���y��{�i�I�Ƀh�C�c�Ɏ������݁A���W�����܂����B���ɁA���@�C�I��������p�����R���\�[�g���y��@���Ȃɂ͖��Ȃ������A�R���[������Ȃ��Ă���A�o�b�n�̃J���^�[�^(BWV27)�̂Ȃ��ɂ��ނ̍�Ȃ����R���[�����g���Ă��܂��B�ނȂ��ł́A���̌�̃h�C�c�o���b�N���y�̔��W�͂����炭�Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�`�g�����̍�ȉƂ���D���ŁA�ȑO�ɂ́u�N���h���E���[�[���~�����[�v�Ƃ����A���T���u����g��ł������Ƃ�����܂����B���ł��A�L���ŁA���t�����p�x�������u�g���I�\�i�^�@�z�Z���v�͂��ăN�C�P���Z��̖����Œ����Ĉȗ��A���́u18�ԁv�ɂȂ�܂����B������A�a�b�i�ł��ނ̍�i�����グ���邩������܂���B �@�V���~�b�g�q���[�[���̂b�c�A�܂��ă\��CD�Ƃ����̂͂��̎��͂ɔ����Ĕ��ɏ��Ȃ��悤�ł��B�����m�����A�w�����F�b�w�Ƒg�o�b�n�̃J���^�[�^�i198�ԑ��j�ƁA���̂b�c���炢�ł��傤���B���Ƃ́A�䂪�a�b�i�Ƃ̈�A�̘^���B���ꂾ���ɁA���̂b�c�̓V���~�b�g�q���[�[���t�@���Ƃ��Ă͐�ɒ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��b�c�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �i�D���[�[���~�����[�@�u�G���~�A�̈��́A�g���I�\�i�^�W�v�icpo�@999 387-2) I�D�V���~�b�g�q���[�[��,�AParnassi musici |
�@Robin Blaze�̂b�c��Q�e����������܂����B�w���f���̃I�y���uRodelinda�v���uUnulfo�v�����̂��Ă��܂��B�A���A�͂R�Ȃ�������܂��A���V�^�e�B�[���H�ł͑�ςɏo�Ԃ������̂ŁA�ނ̉̐���m���ł͎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B�ȑO�ɏЉ��Blow�̓o�b�n�����ꐢ��O�̍�ȉƂł������A�w���f���͌����܂ł��Ȃ��o�b�n�̓�����l�B�܂��A�O�b�c�ł͍����̒��ł̃\���X�g�Ƃ��������ł������A����͊��S�ȃ\���X�g�B���ꂾ���ɁA�ނ��ǂ�ȃo�b�n���̂��������̂b�c���炠����x�����������邱�Ƃ��ł��܂��B �@���ꂩ��A�c�O�Ȃ���ނ̌o���͍ڂ��Ă��Ȃ��̂ł����A�ʐ^���f�ڂ���Ă��܂����B��ςɎႭ�Đ^�ʖڂł���₩�Ƃ����������ł��B�̂����Ղ�����l�B��X�����A�D�����āA�������̂��̂ʼn����m��Ȃ��B�ł��V�g�Ƃ�����������Ȃ��ȁB�����܂ł��u�j�v�������������Ƃ����������B�Ȃ̂��������邯�ǁB �@���t�S�̂��������߂Ƃ����قǂł͂Ȃ��̂ŁA�w���f���A���ȊO�̕��ɂƂ��Ă͂킴�킴�����Ē����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ǂ����Ă����O�ɔނ̉̐����Ă��������Ƃ������͂ǂ����B(�ȂǂƏ����܂������A�C�M���X�ł͌��\�]���Ȃ悤�ł��B����ɉ���������Ă���ƁA��͂�A�w���f���A���̌��������B���r���N�����\�������A�w���f�����D���ł��܂�Ȃ��Ƃ����l�͂����߂��Ȃ��Ă������肪�o�������u���ԂȂ��v�b�c�ł��B�j HANDEL�uRodelinda�v�@�ue��g���� veritas 7243 5 45277 2 2 �J�E���^�[�e�i�[�FRobin Blaze�� Ragian baroque Players, Nicholas Kraemer(direction)
(98/05/29�v�킸�X�V98/05/04)
|
�l�D�g��������(1737-1806)�uSacred Choral Music�v�@�a�h�r�@�b�c�|�W�T�X�@ �@�P�X�X�W�N�x�a�b�i������t��ɏ��o��̃\�v���m�̎�A�~�A�E�[���\���iMiah Persson)�B�ޏ����q�D�a�����������l�A���{�ł͑S�������̑��݁B�����m��܂���ł����B��������̂͂��B���܂܂ňꖇ���b�c���Ȃ������̂ł�����B���́A�ޏ����a�b�i�o���O�ɂ��ɂb�c�f�r���[���ʂ����܂����B���ꂪ���Љ��b�c�ł��B�a�h�r����S���ɔ������ꂽ���̂b�c�͗L���Ȃi�D�g���������̒�A�l�D�g���������̏@�������Ȃ��W�߂����̂ł��B�ނ́A�̑�ȌZ�̉A�ɉB��Ă͂��܂����A�@�����y���ϓ��ӂƂ��Ă���A�݂��������ςɔ������������̎�ł������Ƃ̂��ƁB�����ɂ��ÓT�h�̍�i�炵���A�o�b�n�̂悤�ȋٔ����������͂��܂�Ȃ��̂ł����A�ȑf�Șa���ƁA���܂�������_�Șa���]���A�s���a���̎g�p�ȂǁA���[�c�@���g�ɂ����Ȃ��炸�e����^�����Ǝv�킹��悤�ȍ�i�ł��B����ł��āA�Έʖ@�̎g�����Ȃǂ́A�o���b�N����̑�ƁA�w���f���Ȃǂ��v�킹��Ƃ��������A�o���b�N����ÓT�h�ւ̈ڂ�ς������������Ă���܂��B���ꂩ��A���̂b�c�ɂ͌��y�킪�g�p����Ă��炸�A���ׂĖ؊NJy��ƃg�����{�[���Ƃ����I�P�̕Ґ��ɂȂ��Ă��܂��B�ÓT�h�̖؊ǃA���T���u���̗ǂ����ő���ɐ�������Ă���Ƃ����������ł��B�g �p�y��͂������Êy��B �@���āA�̐S�̃~�A�E�y�[���\���ł����A�a�h�r�����@�����V���������ŁA���܂␢�E�I�Ȓc�̂Ƃ��ėL���ɂȂ����a�b�i�ɓo�ꂳ���邱�ƂŔ��荞�����Ƃ������ƂŁA�a�h�r����̋������E�������������ł��B�a�b�i�ɂ��A���łɑ����̂b�c�ʼn̂��Ă���̎���A�܂��܂������ŐV�N�Ȏ��͂���̎���N�p���A��ĂĂ������Ƃ����l��������A����́u�唲�F�v�ɂȂ����悤�ł��B�a�h�r�Ƃ������R�[�h��Ђ͂��Ƃ��ƍ˔\����V�l���J�A���ɑ���o�����ƂɊւ��āA��ϒ�]������܂��B���ł̓��W���[�ȃ��[�x���ɈڐЂ��Ă��܂����悤�Ȗ����t�Ƃ������A���Ă͂a�h�r�̂����b�ɂȂ����悤�ł��B��炪�a�b�i��ėǂ���Ƃē����B�S�������́A�������ɓ��̓����̂ǂ��l���Ă����[���b�p�Ŕ��ꂻ�����Ȃ��悤�Ȃa�b�i���J�A���W���[�Ȓc�̂ɂ܂ň�����������r�͑債�����ł��B���c���������Ȃa�h�r�̎�r��������ŁA�a�h�r�ɂa�b�i��������B�����āA���x�̓~�A�E�y�[���\���̉\���ɓq���Ă݂悤�Ƃ����킯�ł��B �@���̉̐��ł����A���[�݂̂����ςɏ_�炩�����Ƃ�����ۂł��B������������܂��B�̂��Ă���̂����e����Ȃ̂ŁA���ꂪ�h�C�c��ɂȂ�Ƃǂ��Ȃ̂��킩��܂��A�����炭�k���[���b�p�n�ł��傤����A���قǖ��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�b�c�̖`���ł����Ȃ�̂��͂��߂�̂ŁA�����ɂ킩��Ǝv���܂��B���Ƃ͎��ۂɒ����Ă݂ĉ������B 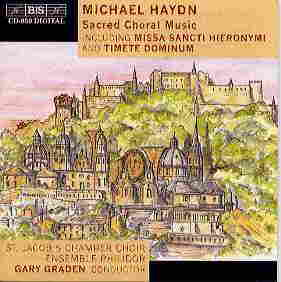 �@�l�D�g��������(1737-1806)�uSacred Choral Music�v�@�a�h�r�@�b�c�|�W�T�X(���̂Ƃ���A���Ղ����ł��j sop:Miah Persson�� �����FSt.Jacobs Chamber Choir�A��y�FEnsemble Philidor�A�w���F�f�������@Graden |
�Җ]�̕ėǁ��a�b�i�̃x�X�g�A���o�������ɓo�ꂵ�܂����B �@�u�o���b�N�A���A�W�i�M��u�V��̐��v�j�v�Ƒ肷�邱�̃A���o���́A���܂܂łɂa�h�r���甭������Ă����a�b�i�̂b�c�̒�����A�ėǂ��o�ꂷ��A���A�A�f���G�b�g���W�߂����̂ł��B�u�ėǂ���̃o�b�n�͒����Ă݂������ǁA�J���^�[�^�͂�����Ɠ�����v�Ƃ����Ăb�c�w�������߂���Ă����t�@���ɂƂ��ẮA����y�ȂP���B�c�O�Ȃ��獡�̂Ƃ���͗A���Ղ݂̂ł����A�����Ղ������\��ł��i�T���H�j�ėǂ���̑��ɂ����c����A���V�����Ȃǂ��o�ꂵ�܂��B����ɁA�������̃J���^�[�^��V���̂����̕������������Ƃ��ł��܂��i��P�R�Q�ԁj�B���ꂪ�Ȃ��Ȃ������B �@�Ƃɂ����A�ėǂ���̐��A���y���Ƃa�b�i�̉��F�A���y���������ɂ������藈����̂ł��邩�B���̂b�c���Ă���������悭�킩��Ǝv���܂��B�a�b�i���ėǂ̉��t�������Ƃ̂Ȃ��ėǃt�@���̊F����ɂƂ��ẮA�ėǂ�����ŕK���̂P���ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�I �i�Ȗځj �o�b�n�^�J���^�[�^��T�S�ԁi�S�ȁj�A��P�R�Q���i�������j�A��P�U�P�ԁA�P�U�Q�ԁA��P�Q�Ԃ��� 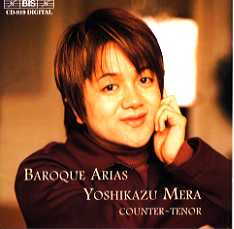 �w���f���^���T�C�A���� �A�[���^�u�C�G�X��Â��z����v���� �V���b�c�^�@���I�����ȏW���� �uBaroque Arias�|Yoshikazu Mera�vBIS-CD-919 �M���u�V��̐��vKI-BIS KKCC2270 �����u���Ȃ�F��v�Ƃ����M��Ń����[�X�����\�肾�����悤�ł����A������������Ă݂����u�V��̐��v�B�����������u�����v�̃W���P�b�g�ʐ^��v�����[�V�����r�f�I�����Ă��A���R�[�h��Ђ͂ǂ����Ă��u�V�g�v�̃C���[�W��蒅���������悤�ł��B�����������܂ł��Ȃ��Ă������Ǝv�����ǁE�E�E�B
����ȕėǂ���̏Ί炪�܂��������I
�i98/05/22�X�V�j
|
�@�U������ėǔ��ꂳ��ɂ�����Ăa�b�i�ɓo�ꂷ��R.Blaze�B���{�ł͑S�������ŁA�܂����u��̃J�E���^�[�e�i�[�v�B���͐��N�O�ɂ���L���ȌÊy�O���[�v�i�t���b�g���[�N�H�j�Ƌ��ɗ����������Ƃ�����Ƃ�����������܂��B�����ŁA����Ȕނ̔閧�������������ׂ��A�r�܂̂g�l�u�ɔނ̂b�c��T���ɂ����܂����B�C�M���X�l���Ƃ������Ƃ͂킩���Ă����̂ŁA�����ɂ��ނ炪�̂������ȃG���U�x�X��������p�[�Z�����炢�܂ł̂�����b�c�����Ă݂܂������A�ނ̖��O�͂���܂���B���ɁA�X���ɂ����Ă��������t�Җ����猟���ł���J�^���O�����āA�悤�₭�����B�����ꖇ��������܂����B1995�N�ɘ^�����ꂽ�i�D�u���E�̃A���Z���W�ł��B���������āA��������Ă݂܂������A�c�O�Ȃ���ނ̏Љ�͑S���Ȃ��B�d�����Ȃ��̂ŁA�A��Ă�����ۂɐ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���S�ȃ\���Ƃ������A�����̒��̃\�������Ƃ������ƂŁA���܂�o�Ԃ��Ȃ������̂ł����A���̂킸���ȏo�Ԃ�������ł́A��͂�A�C�M���X�̓`���I�Ȕ����@�̃J�E���^�[�e�i �[���Ƃ����C�����܂����B�ǂ��炩�Ƃ����ƁA����قǂȂ܂߂������Ȃ�J.Bowman�Ƃ����������ł��B�����͌��\�������肵�Ă��ė͋����A���ʂ���r�I���肻���ł��B�����A�\���͂܂��܂��e���ŁA���P���ɂȂ邫�炢�͂���܂��B�ėǂ���Ƃ͑S���^�C�v���Ⴄ�Ƃ����Ă������ł��傤�B�J���^�[�^�̃\���Ƃ������A�A�[���A�V���b�c�A�u�N�X�e�t�[�f�Ȃǂ̏��K�͂Ȑ��y�A���T���u���ŁA�������������Ƃ��悭�o����^�C�v���Ǝv���܂����B�������A�����̍��C�M���X�o�g�����̂��Ƃ͂���܂��B�������A����͂����܂łb�c�ł̘b�B�������o�b�n�ł͂���܂���B��͂�A���ۂɒ����Ă݂Ȃ��Ɖ��Ƃ������܂���ˁB �@�C�M���X�̃J�E���^�[�e�i�[�E���A���l�҂�J.Bowman�AM.Chance���͂��߂Ƃ��āA���炵���J�E���^�[�e�i�[�������Ђ��߂������Ă��܂��B���������Ȃ��ŁA�V�l���b�c�Ȃǂɓo�p�����@��͔��ɏ��Ȃ��A�܂��A����Ǝv���܂��B�������A�m���ɏo�Ԃ͂܂����Ȃ��ł����A�ԈႢ�Ȃ��AR.Blaze�͏����I�ɂ͊y���݂ȉ̎�ł��B�a�b�i�̃J���^�[�^�W�ւ̏o�������������ɁA�C�M���X���\����J�E���^�[�e�i�[�Ƃ��Ċ���悤�ɂȂ�\�����Ȃ��Ƃ͌����܂���BP.Kooy�������������Ƃ��l���āA�ނ𐄑E�����̂�������܂���B�j�|�P�i�ɐ^���j�̑��l�ҁA�A���f�B�E�t�O�����{�Ŋ��A���ꂩ��ꍑ�X�C�X�ł��L���ɂȂ�A���݂ł͕ꍑ�̉p�Y�ɂȂ����̂Ɠ����悤�ɁAR.Blaze�����{�̂a�b�i�Ŋ��āA�����āA���E�ɂ͂����Ăق����B�ėǂ��a�b�i���琢�E�����đ����Ƃ��Ƃ��Ă��邢�܁A�܂��A�V�����\�����a�b�i����Ă悤�Ƃ��Ă���B����������AR.Blaze�̐��̉̐��ɐڂ��������̂ł��B�i98/03/10�j J.Blow �uAnthems�v �@R.Blaze, J.Cornwell, W.Kendall, S.Varcoe, S.Alder THE PARLEY OF INSTRUMENTS �w���FD.HILL (hyperion CDA67031/2) |
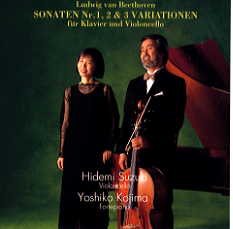 �i�t�H���e�s�A�m�ƃ`�F���̂��߂̃\�i�^�j �u���R�[�h�|�p���I�v �i�a�l�f�W���p���FBVCD628�j �@��؏G���������M�̐V�^���B�c�g�l�ł̓o�b�n�̖����t�`�F���g�ȁA�V���[�x���g�̃A���y�W���[�l�\�i�^�ɑ����^���B�t�H���e�s�A�m�̓A���y�W���[�l�ɑ������Ȃ��݂������F�q�����B �@�N���I���̘^���̎��A�킴�킴�������ɋ߂Â��Ă��āA�u�P���Q�P��������ˁv�ƔO�������悤�ɔ��������������ɋ����Ă���܂����B�u�u�h�u�`�I�a�b�i�ɍڂ��Ăق����v�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B������͂Ƃ����̐̂Ɍf�ڂ��Ă���̂ɂˁB��قǂ����o���ŁA��葽���̐l�ɒ����Ăق����Ƃ����v�������������̂ł��傤�B �@����Ȃ��Ƃ������āA���������b�c���Ē����Ă݂܂����B����Ƃ�͂莩�M�������Ċ��߂邾���̂��Ƃ͂���B���ɋC�����̂������t�ł��B�O��̃A���y�W���[�l�\�i�^���Ƃɂ����������āA�C�i�ɖ������Ă��Ă���ɐF�C�������āA�����ĉ��ƂȂ����߂����������鉉�t�������̂Ƃ͑ΏƓI�ȕ��͋C�ł��i����̂����i�Ƃ����킯�ł͌����Ă���܂��j�B�`�F���\�i�^��P���͂��}���C���ŁA�t�H���e�s�A�m�𗧂ĂĂ���Ƃ��������Ȃ̂ł����A�w���f���̎��i���_�X�}�J�x�E�X�j�ɂ��ϑt�������肩�珙�X�ɔ���Ă��āA�������`�F���\�i�^��Q������C�ɔ�������Ƃ����������ł��B�G������炵�������ɂ悭�o�Ă��鐨���������Ă̂т̂тƂ������t�ł��B�����čŌ���u���J�̎��ɂ��ϑt�ȁv�B������͎��̂��C���[�W�������āA�y���ŏ��X�����ڂȂƂ��������������Ȃł����A�G�������̉��t�́A�Êy��̉��F�̓����������܂��āA�x�[�g�[���F���̉��t�Ɏ��܌�����悤�ȁu���_��`�I�v�ŋX�������t�Ƃ͈�����悵���A�Ȃ��{�������Ă� �鐫�i�Ƃ������̂�f���Ɉ����o�����A�Ƃ��Ă��y�������t�ł��B �@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�Ƃɂ��������Ă��Ċy�����C���ɂ����Ă�����A����Ȃb�c�ł��B����F����������Ă݂Ă��������B �@���ꂩ��]�k�ɂȂ�܂����A�����Ŏg���Ă���t�H���e�s�A�m�̒������A�a�b�i�ɂ����ܓo�ꂷ��K���o�t�҂�����G�������S�����Ă��܂��B
�i98/02/06�j
�{�b�c�����L�O!!��؏G���������F�q�R���T�[�g�I���@�@1998�N3��26��&27���J�U���X�z�[���@�x�[�g�[���F��/�`�F���\�i�^�P�`�R�ԁ��A���y�W���[�l�\�i�^ �@�@�u�]���̃x�[�g�[���F�������A�V�N�Ȕ����Ɗ����v�ڂ������������@�@ |
�@�o�b�n�̃}�^�C���Ȃ͌����܂ł��Ȃ��o�b�n�̍ō�����B���t�ƂɂƂ��Ă͓���ł���A�����č����Č������R�ł�����B���R�A��������̂b�c�����܂܂łɔ�������Ă��܂����A�ŋ߂̂͂��́A��͂�Êy��ɂ�鉉�t�ł��B�����āA1���A�V����2�g�̂b�c�����ɑ���o����܂����B���R���Ƃ͎v���܂����A�Q�g�Ƃ��I�����_�̒c�́A�������Êy��B�����o�[���I�P�̎�v�����o�[6�l���d�����Ă��܂��B
|