
ひとりごと番外編
鈴木秀美の通奏低音の魅力に迫る
〜ラウリン&鈴木兄弟のヘンデル「リコーダーソナタ」より〜
| とっても親しみやすいヘンデルのリコーダーソナタ。譜面づらはとても単純です。しかし、単純なものを「楽譜に書いてある通りに、しかも音楽的に演奏する」ことほど難しいことはない。単純な楽譜を表面的に読んで漫然と機械的に演奏してしまうと、単純な音楽が「単調」なものになってしまいます。果たして、われらが鈴木秀美さんは、この単純な曲をどのように料理してくれているのでしょう。きっと、聴けば聴くほど単純な音楽の「奥の深さ」が感じられて、その魅力にとりつかれると思いますよ。 |
(99/04/28)
《目 次》
| 曲 名 | 楽章 |
| HWV369 F-DUR | 第1楽章 |
| 第2楽章 | |
| HWV365 C-DUR | 第3楽章 |
| 第4楽章 | |
| 第5楽章 | |
| HWV362 a-moll | 第1楽章 |
| スペシャルおまけ | |
| 第2楽章 | |
| HWV367a d-moll | 第5楽章 |
| まとめ |

例によって、まず楽譜からはじめます。これを見ればわかるとおり、小学生でも吹けそうな単純でやさしい旋律。4分音符の「音階」みたいなものですからね。でも、これをただベタベタ同じように弾いてしまったら、または、全部を6小節目のように区切って演奏したら、どんなにつまらなく、おかしなものになってしまうでしょう。適切なアーティキュレーションが施されて、はじめてまともな音楽になります。上の楽譜のアーティキュレーションは、秀美さんがCDで採用しているものです。たった9小節でもこれだけ多彩な区切り方があるのがおわかりいただけると思います。
「ヘミオラ」というのは、3拍子系の曲で、「2小節で3拍」。上の場合なら、「2小節で2分の3拍子」になることをいい、ヘンデルや師匠格のコレルリが非常によく使った手法です。「4分の3」が「2分の3」になるわけですから、単純に音価が倍になると考えればいいでしょう。このリコーダーソナタ集でもかなり多用されています。でも、何も知らない人がこの楽譜を見ただけでは、ヘミオラとは気がつきません。しかし、バロック音楽の作曲技法に精通している秀美さんなら、これは簡単に見分けられます。どうやって見分けるかというと、リコーダーの旋律です。このようなリズムは、ヘミオラの場合の「決り文句」というほど一般的なものです。さて、このヘミオラは、曲の終わりによく使われます。速い楽章の場合には、これによって、あたかもテンポが半分に落ちたような感じになります。ところで、モダン楽器の伝統的な奏法では、ヘミオラを意識せずに、しかも極端なリタルダンドをすることが非常に多いことはよくご存知だと思いますが、これは、どう考えてもおかしい。ヘミオラによってすでにテンポが落ちているのに、さらにリタルダンドをしても意味がありません。単純に半分ではなく、もっと遅くしたい場合には、ヘンデルの合奏協奏曲のように、ちゃんと「Largo」とか「Adagio」と指定があるか、または、楽譜に「2分の3」と書いてしまうこともあります。ヘミオラの効果を高めるためには、テンポを絶対に変えないことが演奏上のポイントです(もちろん、曲の最後にはちょっとはリタルダンドしますが)。秀美さんも、もちろん、この流儀にしたがっています。これによって、単純なリズム、拍子が生き生きとしてくることに気がつくと思います。
こんなちょっとしたことでも、知っているかいないかでは大違いです。

もうひとつ。これはなかなか複雑です。19小節目以降。リコーダーパートを見ると、「秀美流」となっている方が、通奏低音のアーティキュレーションとしては適切なような気がしますが、通奏低音パートだけを見ると、特に和声的(響き)の面から「別の可能性」のようなこともありうるのではないかと思われます。実は、秀美さんは、この2つの可能性のどちらのいいところも生かしています。なかなか言葉で説明するのは難しいのですが、21小節目の頭のFを響かせたままで、2拍目以降の音を別物として弾く。移弦もあるので別物に聞こえますが、しかし、Fが響いているので、「秀美流」のようにも聞こえる。こういう技法は、無伴奏チェロ組曲などでもよく使います。ここまでくると、かなり難しい技術であることがわかると思います。たかが4分音符でも・・・。
(99/04/29)

この楽章も、バスはひたすら8分音符でリズムを刻んでいるのですが、それだけに、色々とやりようがあってオモシロイと思います。なかなか楽譜で秀美さんの弾いているように表現するのは難しいのですが、何となく感じはつかんでいただけると思います。この楽章では、隣り合わせの音が2度で動く場合に、その2つ(または3つ)の音をひとつのかたまりとしてつなげて弾いています(3小節目以降)。

後半の冒頭でも、同じように弾いています。秀美さんは、普段はあまりこういうのを強調する方ではないのですが、リコーダーのアーティキュレーションに合わせているというのもあるのでしょう。それでも、ちゃんと、1拍目はそれとわかるように弾いているところがさすがです。このようなアーティキュレーションをつけると、ともすれば、拍子や和声がわからなくなってしまって(シンコペーションの様に聞こえてしまう)、結局、ぐちゃぐちゃになってしまう危険性があるので、通奏低音パートは、上声部に付き合いながらも、きちっと強拍は抑えておく必要があるのです。つまり、ここでも相反する2つの要求を共に満たすよう演奏しなければならないわけです。
(99/04/30)
実は、私にとってこの地味な楽章こそが、このCDの中でもっとも衝撃的でした。もちろん、リコーダーソロではなく、チェロの音型の弾き方です。

この音型は、コレルリやヘンデルのソナタには頻繁に現れる「決り文句」的なもので、ひとつの楽章でずっとこの音型を弾きつづけるのが普通です。この楽章でも、調性こそ変わりますが、
基本的にはずっとこの調子です。2分近くもこんなに単純なことを弾いているのですから、逆にどう弾くかにとても気を使います。
70年代以降、古楽器奏者達は、秀美さんの師匠ビルスマも含めて、この音型は、あたかもゆっくり歩く様に、比較的短めに、かつ、強拍でも長くしたり強調したりせずに、均等に弾くというのが一般的だったように思われます(歩行低音などと呼ばれることもあるようです)。しかし、秀美さんは、あえてそういう解釈をせず、普通の3拍子として、1拍目を長めに弾いています。なぜこのような解釈をしたのかはよくわかりませんが、少々驚きでした。ただし、ずっと同じような調子ではなく、時と場合によって弾き方を使い分けているようです。

9小節目以降では、2拍おきに長めに弾いています。おそらく、上げ弓になっているときにそうしているのでしょう。もちろん、意識してそうやっているのだと思います。普通はまずこのようには弾きません。そして、この曲全体を「下げ弓−上げ弓−上げ弓」ではなく、「下げ弓−上げ弓−下げ弓、上げ弓−下げ弓−上げ弓」(いわゆる「弓順」)で弾いているように聞こえます。古楽器の場合には、割合と上げ弓と下げ弓は聴いていてその音色の違いがはっきりとしているので、音だけである程度ボウイングの推測はつきます。モダン楽器では、このような上げ弓と下げ弓の音色の違いがでないように訓練するのですが、バロックでは、「違いがあることがいい」とされ、その違いを生かした演奏がなされます。そして、弓の使い方(ボウイング)も、国によって違います。上記のようなボウイングは、いわゆる「イタリア式」ですが、これがフランス、例えばリュリのオーケストラなら、「下げ弓−上げ弓−下げ弓、下げ弓−上げ弓−下げ弓」とひたすら続けることでしょう。これによって、常に1拍目が強くなり、宮廷舞踏の伴奏にふさわしいものになるというわけです。しかし、イタリアではメロディーの滑らかさがより重視されますから、なにも、常に1拍目が強調される必要はありません。そして、ボウイング技法も比較的自由です。

これは、もうおなじみヘミオラです。もちろん、強い音は下げ弓で弾きます。一見、先の例と同じように見えますが、全然違うものです。
こんな調子で、結構色々やっているような感じです。そして、さらに、この曲では、チェンバロも色々やっていますから、それらの相乗効果で、ワンパターンでも飽きさせないのです。
(99/05/01)
HWV365 C-DUR 第4楽章
この楽章には、「A tempo di Gavotti」(ガヴォットの速さで)という指定があります。これは、いうまでもなく、速さだけがガヴォットと同じというわけではなく、「ガヴォット風に」と考えた方がいいでしょう。バッハにもこれと同じ指定がなされた曲がいくつかあります。パルティータ第6番BWV830の第6曲もそのひとつです。ここで、当然のことながら通奏低音は、ガヴォット特有のリズムで演奏しています。ガヴォットなどというのは、ヴァイオリニストなら「ゴセックのガヴォット」、無伴奏チェロ組曲をはじめとしてバッハの数々の曲にも登場するなど、超有名な曲があって誰でもその名前は知っていますが、その特徴や、踊りについて知っている人はほとんどいません。たいていの音楽家は、譜面づらが易しいせいか、何も知ろうとしないまま、自分の思いつきだけで適当に弾いてしまいますが、古楽器奏者は当然ながらそういうことはしません。もちろん鈴木兄弟もです。下の楽譜は、ガヴォットの特徴と鈴木兄弟の演奏をわかりやすく示したものです。

ガヴォットは、2分の2拍子で、その2拍目から始まります。そして、次の小節の頭に重みがきます。これを、2拍目から始まるということでそこに重きをおいて、次の小節の1拍目を軽く弾く人がいますが、それは明らかな間違いです。
無伴奏チェロ組曲第6番のガヴォットも原則的には同じです。しかし、バッハのころになると、必ずしもいつも規則通りとは限りません。でも、やはり、舞曲の基本的な性格は残しています。
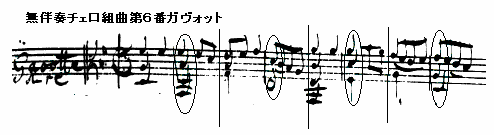
このヘンデルのソナタも「ガヴォットのテンポで」と書かれていることからもわかるとおり、純粋なガヴォットではありません。特に、後半部分は、必ずしもガヴォットのリズムが明確ではありません。秀美さんは、ここでも一貫して1拍目に重きを置いていますが、それは純粋なガヴォット風の部分とはやや趣が異なるような気がします。

こんな部分を経て、再びガヴォットに戻ります。ほんの些細なことではありますが、そういうところにも気を配って演奏すると、全体的に聴いた感じがガラっと変わってくるから不思議です。リコーダーを聴いていてもわからないことはないのですが、よりはっきりとガヴォットの特徴が聴き取れるのはやはり通奏低音です。そして、本物の古楽器奏者とそうでない音楽家の違いがはっきりと出るのも、こういうところなのです。もちろん、皆さんが今聴いているのは「本物」ですね。
(99/05/02)
この曲も単純といえば単純。しかし、一見同じように見えるものでもいくつかのパターンがあって、それを弾きわけなければなりません。例えば9小節目以降。リコーダーはその前と同じことを繰り返していますが、バスは音型が変わります。しかし、基本的な構造は変わっていない。前のものを感じながら、より細かい音符にしているのです。

ここでは2小節ごとにアクセントの場所が違います。最後のヘミオラですが、よく聴くと毎回微妙に弾き方が異なることに気がつきます。ヘミオラであることさえわかれば、後はある程度自由に弾けるようです。

17小節目からは、1、2拍目にアクセントが来ています。2拍目には「6」という和音を表す数字が書いてあります。ここで和音が変わることがわかります。チェンバロをよく聴いてみてください。

33小節目からは1、3拍目にアクセントが来ています。3拍目に数字が書いてあります。チェロではほとんどわかりませんが、チェンバロを聴けばこのことは明らかです。リコーダーを見ると、本来はここは1拍目だけにアクセントがある(チェロのように)と思うのですが、和音が変わるが故に、あたかも3拍目にアクセントが来ているように感じられるのです。「和音が変わる」ということにはものすごく深い意味があるのですが、今回は詳しいことは省略しましょう。「鈴木秀美ワークショップ」でも説明があると思いますから、それを聞いてください。要は、「和音が変わるところ」に要注意ということです。そして、同じ3拍子の曲でも、しょっちゅうビートの場所が変わる。それを感じとって、きちっと表現しなければならない。そうすることによって、単純な曲が変化に富んだ生き生きとした曲になるのです。とはいっても、何の根拠もなく、むやみに変なところにアクセントをつけるのも考えものです。最近の古楽演奏の中には、普通では考えられないような場所に変なアクセントをつけて、奇をてらったような演奏が少なくないようですが、そういうのは最初は驚いても、だんだん飽きられてきて、やがて嫌悪感をもよおすようになるでしょう。不協和音や特殊な和音を強調するとか、そういうきわめてバロック的なものならいいのですが・・・。
バロック音楽は、もともと和音の使い方とビートに関してはきわめて刺激的に作られています。だから、オーソドックスに演奏したとしても、作曲家が意図した「刺激」さえきちっと抑えていれば十分に刺激的なはずです。それを別のところでさらに変なことをする必要性はあまりないような気がします。その点、この演奏はオーソドックスでありながら、勘所はきちっと抑えている。そういう演奏だといえます。
(99/05/03)
ヘンデルのリコーダーソナタのCDと聞けば、まず最初にヘンデルらしい明るくておおらかな曲が来るものだと期待してしまいますが、それを見事に裏切って、なんともけだるいといおうか、暗いといおうか、そういう不思議な感覚の曲を持ってきました。
このけだるさ、やはり、チェロの弾きつづける低音のリズムがその原因かな。ということで、このワンパターン低音について考えてみたいと思います。
まず、この曲が4分の3拍子で書かれているということを考えなければなりません。

しかし、楽章全体を通じて3連譜がなりつづけています。表面的には4分の3拍子というよりは、8分の9拍子のように聞こえます。そして、楽譜を見ながら聴くとよくわかるのですが、付点音符の長さ、8分音符や16分音符の入るタイミングなどが、楽譜に書いてあるのとかなり違うことがわかります。1小節目のリコーダーの8分音符と通奏低音の3連譜の最後の8分音符、この両者は同じ8分音符ではありますが、通奏低音の方は3連譜ですから、普通なら当然違ったタイミングで鳴るはずです(リコーダーのほうがやや早く出る)。しかし、この演奏では、ほぼ同じタイミングで鳴っています。
 |
 |
5小節目では、リコーダーの8分音符と通奏低音の16分音符、次の小節ではリコーダーの3連譜の最後の8分音符と通奏低音の16分音符がほぼ同一タイミングで鳴ります。41小節目も似たような感じですがここでは8分音符ではなくて16分音符で書いています。12、24小節目では、さらに不思議なことがおきます。
 |
 |
12小節目と24小節目のリコーダーを比較してみてください。とても似ていますし、聴いた感じもあまり変わりません。しかし、明らかに別物です。演奏の方もよく聴くと両者を区別しています。24小節目の方では、16分休符のあとの16分音符に入るときに意識して呼吸を合わせ、ピタッと同じタイミングで入っています。それまでは、タイミングが一致しているとはいっても、それは「何となく」という感じだったので、その時の流れによっては、微妙にずれることがありましたが(まるでルバートのよう)、このパターンの時にはそういうことはほとんどありません。
逆に、楽譜上は同じタイミングで出るはずなのに、敢えてずらしているような場合もあります。

このように、モダン楽器の演奏スタイル的意味からは、「楽譜に忠実ではない間違った」演奏ですが、実は、ちゃんとした根拠があってやっていることです。ひとつは付点音符の処理、特に3連譜とからむ場合の演奏について記述したバロック時代の文献にその根拠を求めているわけです。ただ、このやり方がすべての場合に通用するとは限りません。全く異なる見解のものもあります。4分の3拍子は8分の9拍子のように演奏されてはならない。8分の9拍子の4分音符+8分音符と4分の3拍子の付点8分音符+16分音符は違うし、基本的には音符が異なればその音価にあわせて異なった演奏をするべきだという見解もあります。しかし、いずれにせよ、まるで機械で測ったような「正しい」長さで音符を弾くことは、バロック音楽の演奏にはふさわしくありません。というのも、音の持っている微妙なニュアンスを「音符」という記号で完璧に表現することが不可能だからです。特に即興的な装飾音を正確に音符で書きとめるのは不可能なことです。バッハなどは、それをできる限り音符で表現しようと努めましたが、それが今日の一般的な記譜法と異なる独自のものであって、音符の音価をすべて足し合わせると、その曲の1小節の音価(4分の3拍子なら4分音符3つ分)より多くなったり少なくなったりなどということもよくありました。これが、今日の楽譜の校訂者や良心的な演奏家を悩ませているのです。現代譜ではその辺を「解釈」して現代風に直してしまっているので、そういう「おかしい」楽譜に出会うことは少ないでしょうが、それでは本来のバッハの意思を反映しているとはいいがたい。だからこそ、「自筆譜にあたれ!」といわれるのです。
そういう楽譜という記号の集まりの限界を補うのが、当時の演奏家の「よい趣味」、「演奏習慣」であり、それを書きとめている当時の文献の記述です。付点の長さについても数多くの記述がありますが、最終的には、その付点が音楽的に見て何を表そうとしているのかによって決まります。リズムを生き生きとさせたいのか、倦怠感を出したいのか、鞭打ちなのか、舞曲のステップなりからだの動きをあらわすのか・・・。こんなことを「64分音符何個分の長さにする」などまるで機械みたいなことをいって打合せて一体何の意味がありましょう。音楽的な意味をハッキリさせてあとは呼吸を合わせる。ヴァイオリンなら弓の動きをみて呼吸をあわせればいいでしょう。別に難しいことではないのですが、それがなかなかできない。あくまでも「細かい音符にして何個分」と決めないとあわせられないといって納得しない人のなんと多いことか。
ウィーンフィルがウィンナ・ワルツを演奏するときの独特の3拍子のきざみ。どう考えても3拍均等な長さには思えません。では、彼らは各拍を「64分音符何個分」などと決めて演奏しているでしょうか? 絶対にそんなことはないでしょう。生まれた時から体にしみついているので、無意識にそのように弾き、またあれだけの大人数でもピッタリあう。
バロック音楽の場合も同じなのですが、残念ながら当時の習慣がそのまま残っていないので、ウィンナ・ワルツやその他ヨーロッパの田舎に残る習慣などを参考にしながら、当時の文献に書いてあることを具体的に音にするしかない。特に舞曲は参考になります。
ある演奏会のあとに、鈴木秀美さんに「すばらしい」といったら、「楽譜に書いてある通りに弾いているだけさ」というそっけない返事。でも、「楽譜に書いてある通り」がバロック音楽に関してはいかに難しいことであるか。この短いヘンデルの1楽章を見ただけでもおわかりいただけると思います。
(99/05/09)
HWV362第1楽章のように3連譜が多いパターン、実はバッハにもあります。有名なブランデンブルク協奏曲第5番第3楽章がそうです。この曲は4分の2拍子ですが、8分の6拍子のようにも聞こえます。ここでも、付点8分音符+16分音符と8分音符の3連譜のカラミがしばしば登場し、どのように演奏したらいいのか演奏家たちを悩ませています。

上2段がフルート、ヴァイオリン、下2段がチェンバロです。出だしのテーマからこうですから、先が思いやられます。今日では、一般的に3連譜を中心に考え、付点8分音符は3連譜の8分音符2つ分、32分音符は3連譜の最後の8分音符と同じように弾き、しかも、付点らしく生き生きと飛びはねるように演奏するようです。バロックの演奏習慣に「付点は長めに」つまり、強いて今日風にいえば複付点のように弾くというのがありますが、この場合にはその規則は当てはまらないと考えられています。
(99/05/09)
続く第2楽章、今までに聴いたことのあるCDと比べると、なんだかとってもシャカリキになって弾いているような気がする。でもよく聴いてみると「なるほど」と納得。楽譜に書いてある音をすべてそのとおりに弾いているからです。ビルスマもそうだし、以前秀美さんが有田さんたちと録音した時もそうでしたが、楽譜に書いてあるとおりには弾いていない場合が多い。
16分音符は、基本的には和音を分けて弾いているに過ぎない(分散和音)のですが、チェロはそのうち下の2つの音、別の言い方をすれば1番目と3番目の音しか弾かず、チェンバロはすべての音を弾いていることが多いようです。本当のバス声部は4つの音のうち最初の音だけなので、それだけ弾いていればとりあえずはよしということなのでしょうか。これならば、チェロはシャカリキになる必要はありませんが、それでは面白くありません。

鈴木秀美さんは、これを全部弾いています。だからある程度シャカリキにならなければ弾けないし、そうでなければ曲の持つ本来の感じは出ない。ところが、これだけ細かい音を弾いていても、本来のバス声部がはっきりと聞こえてくるのです。そして、この音型が和音であることが認識できるのです。普通ならば、高い音のほうが目立つので、バス声部よりも、他の声部(またはあとの3つ)の音のほうがよく聞こえてしまっておかしなことになりますが、そういうことはありません。これは、最初の音(上の楽譜ではF)と次の音(D)が多くの場合五度以上はなれている、つまり、ヴァイオリン属の調弦は五度間隔ですから、必ずここで移弦が生じるということも多いに関係してきます。例えばFはD線、高いDはA線で弾くことができるわけです。そして、Fを抑えた左手の指を離さずに隣の弦でDを弾くと、Fの音は移弦した後でも響きが残ります。チェロの場合には弦が長く、太いので、あえて弦の振動を止めない限りは、たとえ弓をはなしても響きが残ります。あたかもFが4分音符であるかのように鳴るわけです。さらに、D線とA線では音色が違います。そのことが、D線で弾くFの音を引き立たせます。モダン奏法では、このように音によって音色が変わることは悪いこととされ、それゆえ、開放弦を使うことはもちろん、ひとつのフレーズの中でもできるだけ移弦はしない様にとされます。しかし、古楽器奏法の場合には、音色が違うのもいいとされ、それを逆手にとってしまいます。
バッハの無伴奏チェロ組曲でも和音が多数登場しますが、そこで、バスをどこまで響かせるか、和声を考えながらコントロールします。和音が変わっても前の和音のバスが鳴り響いていてはおかしなことになります。そういう場合には、指で弦の響きをわざと止めるということも必要になります。もちろん、鈴木秀美さんもこのようなテクニックを駆使しています。このヘンデルでもそうです。
一方、チェンバロは、右手で和音を一度に弾くことができます。そして、和音が変わるまで、その音を響かせていればいい。そして、バスの音は、鍵盤を抑えたままにしておけばいい。このようなチェロと鍵盤楽器の共同作業で、バス声部を十分に聴かせながら和音をも認識させることができるのです。
ところで、秀美さんは、耳にはほとんど聴き取れないような細かい動きまで、すべて楽譜に忠実に弾いています。16分音符ですら弾くのが大変というのに、32分音符まで弾くとは。細かすぎてよく聴き取れないのに・・・。ヘンデルがなぜこんな聴き取れないような装飾をいれたのかよくわかりません。

いずれにせよ、「秀美さんご苦労様」と思わずいいたくなる演奏でした。
(99/05/18)
いよいよ最終回。今回はかなり難しいことなので、はたしてうまく説明できるかどうか・・・。
HWV367a第5楽章「Alla Breve」は、ヘンデルのリコーダーソナタの中では珍しい対位法的な楽章。2つの声部がかけあいになっています。
まずはテーマ。どちらかというと単純なものですが、これをリコーダーとチェロで聴き比べてみてください。理屈では単純に模倣すればいいような感じですが、楽器の違いもあってか、微妙に弾き方といおうかニュアンスが違うのがわかります。このテーマはその後何回も出てきますが、その都度違います。リコーダーの切れのよさに対して、チェロの「深み」と「余韻」。味わいではチェロに軍配が上がりそうです。スタッカートで弾くところでは、リコーダーは完全に音が切れてしまうのに対し、チェロでは切っているような切っていないようななんとも微妙な表現ができます。

次に、リコーダーでは度々、チェロでも1回だけ出てくる2分音符がタイでつながっている下降音型。これも単純極まりないものですが、実は、きわめてバロック音楽ならではの特徴を持っています。コレルリのトリオソナタや合奏曲にも最後の一番盛り上がる部分で頻繁に登場します。ここでは典型的な例をご紹介しましょう。同じくヘンデルのトリオソナタOP1-3第4楽章です。

3声ですが、基本的な和声構造はリコーダーソナタと同じです。バス声部に「65」という数字の書いてある強拍では不協和音になっており、それが弱拍で協和音になる。「緊張と弛緩」これの繰り返しです。詳しいことは、和声学に疎いAHがゆえよくわかりませんが、通奏低音の教科書などを読むとそういうことになっているようです。ここで、1STと2NDがどう弾くべきか。一見同じ2拍だから同じように弾くか、または、2NDはシンコペーション風に弾くか、音楽界の常識ではそのどちらかでしょう。しかし、残念ながらそのどちらでもない。まずは、不協和音と協和音では2ND VNの1STへの音の「ぶつけ方」が違います。1STは普通に拍の頭を強く弾けばいいのですが、2NDは、その和音の性格を見極めて、不協和音になっている強拍に緊張感が出るようにしなければなりません。そして、そこから協和音へ向けて弛緩していく。これらと古楽器特有の「メッサ・ディ・ヴォーチェ(いわゆる中ふくらみ)」があいまって、この単純な音型を味わい深く彩っているのです。これを極端に強調する人もいますが、そこまでやらなくても十分に効果はあります。
さて、リコーダーソナタですが、2声なので、上記の例ほどにははっきりしていませんが、バス声部に書かれている数字を見ると、やはり同じパターンであることがわかります。リコーダーパートは2ND VNと同じ働きなので、このタイの後の音までちゃんと伸ばしています。タイの頭にアクセントをつけてそのあとスーッと音を抜くようなことはしていません。ここでは1ST VNがないので、チェンバロの和音や聴き手の頭の中で想像力を働かせてこの変化を楽しむことになります。

そして、ここでのバスですが、同じパターンが何度も出てきますが、毎回少しずつ弾き方、アーティキュレーションが違います。しかし、こちらは1拍目にアクセントを置いています。和音の変化などを考えながら弾いていることは間違いないでしょう。
一方、一度だけリコーダーとバスの立場が逆転する場面があります。46小節目からがそう。

チェロは、2分の2拍子の2拍目には当然のことながらアクセントはつけません。やわらかく弾き始め、ほんの少しごく自然な感じで音をふくらましています。不協和音を強調するあまり、極端にふくらまして、しかも1拍目のところでアクセントをつけたりするとやや下品な感じになってしまいます。そういうのは秀美さんは好みではありませんから、このようにあっさりと弾いているのでしょう。しかし、ただ漫然と音を伸ばしているのとは根本的に違います。歌うことと同時に、和声の変化を楽しむことを大事にしているのです。
和声感覚の極めつけは、やはり最後の部分です。リコーダーが装飾をつけているのでわかりにくいですが、これもものすごい不協和音から、最後協和音に解決して曲を終わるという嗜好です。ここではさすがに秀美さんも不協和音を気持ち悪くなるくらい意識して弾いています。

このように、対位法楽章でも、アーティキュレーションに配慮するだけでなく、和声を意識して弾く。特に不協和音と協和音の変化は・・・。
(99/05/23)
ながながとヘンデルのリコーダーソナタのCDを題材に鈴木秀美さんの通奏低音奏者としての魅力を探ってきましたが、実は、これらのことは鈴木秀美さんの「個性」ではなく、バロックチェロ奏者、いや、古楽器奏者のすべてに共通することなのです。つまり、秀美さんの特徴ではなく、古楽器奏法の特徴なのです。しかし、古楽器奏法なくして秀美さんの演奏は語れません。それをベースに独自の個性を花開かせているからです。古楽器奏法は秀美さんにとって母国語のようなものです。私たち日本人が日本語を話すときには、文法だの発音だの、その他学校で習うような諸規則などはほとんど意識せずに自由に話し、自分を個性的に表現していますね。それと同じように、秀美さんにとっては、古楽器奏法の規則や私が書いてきたようなことはもはや無意識のうちにできること。ましてや、「規則に縛られている」などという感覚は全くないでしょう。
しかし、聴き手である私達は、学校や先生に習ってきた20世紀以来の伝統しか知らないし、それが唯一正しいものだと教えられてきた。だから古楽器奏法がかもし出すこまかい魅力になかなか気がつかない。そして、時には古楽器奏法を「邪道」「伝統に逆らったまちがったもの」として断罪する。それでは、鈴木秀美さんはじめとする古楽器奏者の魅力はわかるわけがない。
「弾いて楽しければそれでいい」「聴いて楽しければそれでいい」そういう考え方もあります。大部分の音楽ファンはそうでしょう。しかし、知識があれば、今まで聞こえなかったようなことも聞こえてくるようになり、気がつかなかった魅力に気がつくということもあります。これは特にバッハの音楽には言えることです。
バロック時代の楽譜を読み、演奏するということは、昔の文法で書かれた古文を読んで解釈するようなものです。19世紀以降の楽譜の読み方、解釈では解決できない問題があまりにも多い。平安時代の「源氏物語」や「枕草子」を辞書片手に昔の文法を学びながら読まなければ意味がさっぱりわからない。それと同じ感覚なのです。それを、20世紀半ばまでのモダン楽器の演奏は、現代の文法と現代語の辞書を片手に読もうとしていた。それを、古楽器奏者達はその時代の文法と単語の意味から解釈しなおした。そういう当たり前のことを当たり前にやり始めた。鈴木秀美さんが「楽譜に書いてあるとおりに弾く」という時には、まさにこういうことを含んでいっているのです。
さて、これは古楽器奏法のホンの一部です。まだまだ数え切れないほどのノウハウがあります。それをもっと詳しく知りたい、鈴木秀美の演奏の秘密を探りたい、そういう方は、是非、「鈴木秀美ワークショップ」を聞いてください。秀美さんはノウハウの出し惜しみは一切しません。バッハの無伴奏チェロ組曲を題材に、彼の持っているノウハウのすべてを語ります。しかし、彼の個性は彼だけのもの。真似しようと思ってできるものではありません。
さあ、もう一度、鈴木秀美さんのソロ、そして通奏低音をじっくり聴いて、その魅力にひたってみませんか?
おわり(99/05/23)