
「イタリア風協奏曲」の不可解さ第一部(3)
「VSOP」なんて20年くらい前の流行り言葉ですが、これがピッタリなのが、バッハのチェンバロ協奏曲の緩徐楽章の通奏低音パート。その一覧をご紹介しましょう。
チェンバロ協奏曲第1番:途中で調が変わることはあるものの、基本的にはワンパターン。冒頭は、全員でこの不気味な旋律を弾く。ソロはまるでイタリア装飾をフルに使った変奏のよう。

チェンバロ協奏曲第3番:ヴァイオリン協奏曲第2番と同じ。冒頭はバスがこの動きをしてあとは長い音符をずっと弾いている。

チェンバロ協奏曲第7番:ヴァイオリン協奏曲第1番と同じ。特徴のあるバス音型がほとんど鳴り続く。ただし、通奏低音とヴィオラで交代あり。ヴィオラがバスを受け持つ場面では「刻み」になる場面あり。冒頭ではヴァイオリンは8分音符の和音だけ。

3台チェンバロのための協奏曲第2番:これもなんだか面白いバス音型が繰り返し出てくる。これはヴァイオリンが別の旋律を弾いているが、存在感はこちらの方がある。

このような低音。実は固執低音とか呼ばれます。シャコンヌのバス音型とか「ラメントバス」なんかもこの仲間といえましょうか。古典派以降の「主題」とは違いますが、曲の「軸」になっていることは確かです。バッハの協奏曲の緩徐楽章では、こういう手法が非常にメジャーなんですね。バスがワンパターンだと、その分、上は自由に弾けるというメリットがあります。即興的にイタリア風装飾を駆使して、変奏のように変化をつけて弾いていくことができるのです。ちょっと違うかもしれませんが、ゴールドベルク変奏曲も冒頭のアリアのソプラノ声部の変奏ではなく、バスの変奏といったほうがいいでしょう。よく聴くと、常に同じバスが鳴っています。このテーマ、後に変奏カノンの主題としても使われています。
さて、これで、第1部チェンバロ協奏曲の研究は終わりです。この成果をもとに「イタリア協奏曲」を徹底分析してみることにしますが、時間がかかりそうなので、しばらくの間このコーナーはお休みします。
第2部「イタリア協奏曲の謎に迫る」にどうかご期待ください!
(99/09/26)
チェンバロ協奏曲ニ長調BWV1054は、ヴァイオリン協奏曲ホ長調BWV1042の編曲。この原曲の第1楽章のソロパートは、ヴァイオリンの重音奏法を駆使してしばしば2声部の掛け合いになっています。これが複数の声部を難無くこなす鍵盤楽器用への編曲ならば、当然、その声部はそのままいかされるはずだろうと誰しも思うのではないでしょうか。しかし、そこはBACH。凡人の期待を見事に裏切ってくれます。なんと一つの声部になってしまっているのです。
95〜101小節にかけてがそうです。

和声的には根本的な変更は加えられていないようなのですが、楽譜を見るとあまりの違いに驚きます。VNとCEMを逆にいわれても素人ではわからないかもしれません(でも、Eisの8分音符を続けるなんて言うところは明かにチェンバロらしくない)。
どうしてBACHがこのような編曲を行ったのかはわかりませんが、ヴァイオリンでやればカッコイイものも、チェンバロでやるととても稚拙に聞こえてしまう場合があるということは言えると思います。チェンバロだとあまりにも簡単に弾けてしまっておもしろくない。そして、ここではRIPIENOの1ST VNがソロの変形みたいな音型を弾いていて、それとソロの掛け合いというのがVN同士だと面白いのですが(両者が全く対等に聞こえる)、これがチェンバロとVNだとあまり面白くない。チェンバロ協奏曲でもRIPIENO 1ST VNパートはそのまま生きているのですが、やはりVN同士の関係とは違うような気がします。
そんなことで、原曲で2声なのがチェンバロで1声ということもあるという例をご紹介しました。
次回からは、VSOP低音について語ってみたいと思います。
(99/09/02)
第3楽章です。なお、この楽章も他の楽章と同様にカンタータのシンフォニアとして使われたという説もありますが、楽譜が残っていないのでわかりません。この楽章はもともと2声部だったものが3声部に一部拡大されているのですが、そういうのとは別に、明らかに通奏低音の弾く和音としての音があります。まずは22小節ソロの部分です。
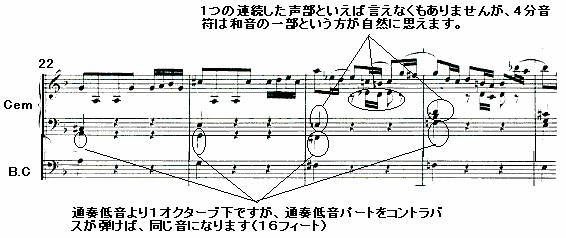
楽譜を見てもそうなのですが、実際に音を聴くと、普通の古楽ファンならだれでも「通奏低音が聞こえる」と感じるに違いありません。他の箇所では、チェンバロのバスは装飾的にかかれていて、通奏低音とは違うことが多いのですが、ここでは、事実上全く同じです。
45小節以降は、それまでとちょっと違うパターンですが、やはり通奏低音的です。そして、珍しくTuttiの所で出てきます。

Tuttiの部分(45、47、49小節)では1st VNと重なるということでsoloパートを弾かずに、通奏低音に徹している演奏もありますが、そこまでやらなくても楽譜に和音が書いてあるので、そのまま弾けばいかにも通奏低音らしくなります。楽譜の中にも書いた8分音符と付点4分音符の両方を兼ねる音。バッハに詳しい方ならこのようなパターンがチェンバロ作品には非常に多いことに気がつくと思います。一方、オルガンではあまり見かけません。これをどのように弾いたか? 鍵盤が2段あれば8分音符を下鍵盤、付点4分音符を上鍵盤などということも可能性としてはあるでしょうけど、Tuttiの部分で上鍵盤を使うということもあまりないでしょうから、現実的には考えにくい。私が思うに、たぶん実際には付点4分音符しか弾かないけど、意識の中ではちゃんとバス声部の8分音符が鳴っているという状態ではないか。いいかたを変えれば、あくまでも8分音符でバス声部を弾く(チェロでいえばデタッシュで)のだけど、付点4分音符の時だけはその音を弾き終わっても指を離さずにそのまま響かせておくということをあらわしたかったのではないか。
この他にも楽譜上はTuttiで同じようなところがあるのですが、必ずしも楽譜通りに弾かず、通奏低音に徹している演奏も多いので、バッハの意図がどうだったのかは良くわかりません。そして、この楽章は実に多くの重厚で力強い和音が頻繁に使われています。これも通奏低音的といえばいえないこともありませんが、通奏低音パートと独立した動きの中で使われることが多いので、ちょっと違うかなという気もするので、取り上げません。
これで、チェンバロ協奏曲のソロの中に登場する通奏低音的和音については終わりにします。以上のことを頭においた上でイタリア協奏曲の楽譜を見ると、実に色々なことが見えてきます。
次回はヴァイオリン協奏曲からチェンバロ協奏曲に編曲した際に行われた、ちょっと変わったことをご紹介します。
(99/08/29)
次は95小節。
ここも和音が補充されていますが、こんどはバス声部及び内声部が最初8分音符、途中から16分音符というパターンです。
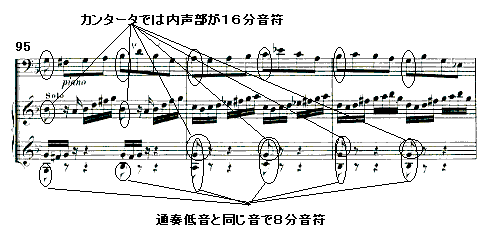
一番上の段が通奏低音パートです。チェンバロの左手は通奏低音パートの上に和音をつけていますが、そこでは、通奏低音パートと同じ8分音符で弾いています。
ところが、このあと98小節からはなぜか左手のバス声部が16分音符になってしまいます。99小節からは通奏低音は逆に長くなって4分音符なのにです。
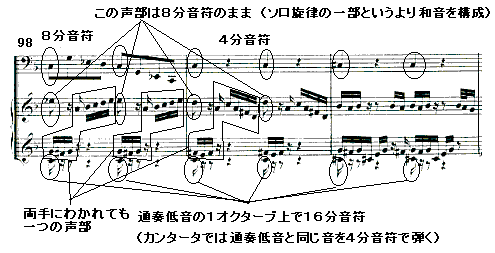
そして、バスの音であるCが16分音符なのに、なぜか和音の構成音である右手の1番高い音(Es,D)は8分音符のまま。もちとん、テクニック上の問題もあるのでしょうけど、「和音の響き」という点から何らかの意図があってこうしたのでしょうか?
この他に162小節にも似たような場面がありますが、これは174小節と同じようなものなので省略します。
これら一連の分析で疑問に思ったことは、チェンバロの左手のバス声部が16分音符、8分音符、4分音符といくつかのパターンがあり、また、それらが必ずしも通奏低音パートと一致しないこと。そして、オルガンで弾かれるカンタータと左右の手の割り振りが違うように思えることです。オルガンの右手パートというのは、ヴァイオリンで弾くのと全く同じような感じで、我々にもしっくりくるのですが、チェンバロの場合には、ひとつの旋律のはずなのに、それが両手に分けられてしまう。特に小節の頭や3拍目のようないわゆる強拍だけがなぜか左手でバスの音とともに弾かれる場合が多い。これらはどのような意図で書かれ、また演奏する上でどのように解釈されなければならないのか。ヴァイオリニストにはなかなか理解できないことです。むろん、ただ機械的にその音価分だけ音を伸ばせばいいというのではないことは明らかです。私の直感からすると、やはり、これらはバスの上の和音の響きをどう作り、そして、オケを含めた上声部をどう支えていくかということに関係があるのではないかという気がしてなりません。
実際の演奏を聴いてみると、例えば82小節のような所は、たとえ16分音符で書いてあっても、強拍ならやや長く響かせて、和音の性格、色がわかるように弾いている様な気がします。むろん、8分音符の時よりは短いですが。そんな風に考えると、和音の場合の音符の長さというのは、絶対的なものがあるわけではなくて、相対的に長めか短めかということを表しているに過ぎないような気がしてなりません。8分音符が16分音符よりは長いとしても、響きの長さとして果たして2倍なのかといわれると首をひねらざるを得ません。そして、同じ音符であっても強拍なら比較的長く響きを保持するし、そうでなければ比較的早く響きをとめる。そんな微妙なさじ加減が鍵盤楽器奏者には要求されるのではないかと思います。そして、もしかしたら、これはヴァイオリニストにもいえるのではないか。
今年5月の今井奈緒子さんが弾いたバッハのオルガンのためのトリオソナタ。これは曲名からもわかるように独立した3つの声部で書かれていて、記譜法もフルートやヴァイオリンの場合と全く同じです。最も低いバス声部は当然のことながら普通のトリオソナタでの通奏低音パートなのですが、数字も書かれていないし、実際の演奏でもバスの上に和音を補充するということはありませんでした。にもかかわらず、不思議なことにバスの上の「和音」が聞こえてきて、あたかももう1人鍵盤楽器奏者がいて、和音を弾いているのではないかと思えるほどでした。そして、昨年聞いた寺神戸さんの無伴奏ヴァイオリン。この対位法の曲の中でもなぜか通奏低音的な和音の響きが聞こえてきたのです。楽譜にはとりたててなにも書いていないけど、大事な和音はやや長めに響かせるとか、そういう普通の聴衆にはなかなか気付かないような工夫をしているに違いありません。
バッハという人は、できるだけ実際の響きを忠実に音符にしようと考えていたふしがあります。特にチェンバロ曲の場合にはそんな気がしてなりません。それに比べると器楽曲やカンタータなどは、かなりいい加減(といおうかそれが普通なのですが)。その記譜法の違いをよく理解しないと、とんでもない誤解をしてしまう可能性があるのではないか。そして、現代の出版譜を見る上では、そういうことも念頭に置いた上で、校訂者がそのあたりをどのように扱っているかも考えなければならない。さらに、楽譜を見ながら実際の演奏を聴く場合には、演奏家がそこに書かれている音符の意味をどう解釈したのかも考えなければなりません。演奏家は必ずしも校訂者の意見をそのまま取り入れるわけではなくて、自筆譜や筆写パート譜などを参考にしながら、当時の演奏習慣なども考慮して自分なりに楽譜を読みます。少なくとも名のあるバッハ演奏家ならそれは当たり前のことで、新バッハ全集すらそのまま無批判に受け入れることはない。まして、旧バッハ全集など参考にもしないかもしれません。鈴木雅明さんが「自筆譜を!」と繰り返しいっているのも、そういうことです。機械的な意味では「不正確」な演奏であっても、音楽的には正しいということもある。バロック音楽というのはそういう余地の非常に大きな音楽なのではないか。そう思えてなりません。
さて、この曲の第3楽章でも和音を補充したと思われるところがいくつかありますので、次回はそれを簡単にご紹介しましょう。
(99/08/15)
まず、第23話を加筆しました。
次は82小節から。これは少々複雑です。まずは楽譜を見てください。
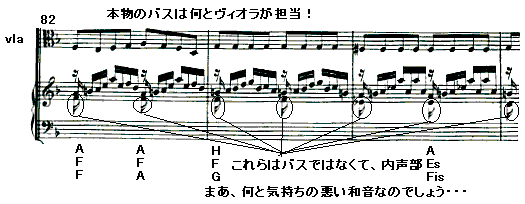
一見、チェンバロの左手の低い方の音がバス声部のように見えますが、実は本物のバス声部はヴィオラが担当しています。ヴィヴァルディでもそうですが、バッハの場合もこういうケースが少なくありません。そうするとチェンバロの左手は和音の内声部ということになります。この声部は16分音符ですが、バスは8分音符。ただ、ヴィオラは当然デタッシュで刻んでいますから音価いっぱいに「ダーダー」引きずるように弾くわけではありません。そして、カンタータではチェロ、コントラバスなどがヴィオラの1オクターブ下、2オクターブ下を4分音符で弾いています。編成が大きいので、これくらい強力なバスの支えが必要なんでしょう。そんなもろもろのことを考慮に入れて、この和音を弾かなければなりません。それにしてもひどい不協和音ですね。カンタータではFis,Es,Aの上にさらにCが乗っています。とにかくものすごい進行です。そのことがわかるように弾かなければならないことはいうまでもありませんが、だからといって、オケでヴィオラだけがバスとして鳴っているような静かな場面で、チェンバロの和音だけ大きく響かせるというのもおかしい。ヴィオラの短めのきざみに合わせて短めに弾きながらも、和声の進行がわかる程度に響かせるという感じでしょうか。
ここでもチェンバロの上声部のAやHは、上声部の一部でもあるし、通奏低音としての和音の一部でもあるわけです。
(99/08/10)
46小節からは一見奇妙な音型です。

本来は以下のカンタータのような音型だったのですが、46小節目の最初の音が4分音符になってしまい、しかも左手に割り当てられたのです。これは単に指使いの都合だけでなく、4分音符の和音を聞かせたかったからだと思われます。左手だけで和音を補充している例です。

ところが、これとほぼ同じ音型が出てくるにもかかわらず、46小節とは異なる書き方をしているところがあります。174小節からがそうです。

ここではカンタータにあったバス声部がしばしば省略され、さらに書かれているところでも4分音符ではなくて16分音符になっています。なぜこうしたのかは良くわかりません。カンタータではバス声部をペダルを使っていたのがチェンバロでは使えないのでそうしたのか、音楽的な理由なのか・・・、通奏低音パートの音型がカンタータと違うからか。
そしてこの部分の最後、182小節では、バスが8分音符に変わり、しかもカンタータにはなかった声部が付け加えられて、和音の響きがより明確にわかるようになっています。

さて、46小節と174小節、182小節では強拍の和音の弾き方を変える必要があるのか、それとも単に記譜上の問題なのか・・。なぜ、同じ音なのに通奏低音は4分音符でチェンバロのバスは8分音符や16分音符なのか。4分音符と16分音符というのは差があまりにも大きいのですが、そこまで響きの面で差をつけていたのか、それとも4分音符の時よりはいくらか響きをとめるのが早いという程度なのか(相対的な響きの長さしか音符があらわしていない)。なかなか判断に苦しむ所です。個人的にはたぶん後者だと思うのですが。
他にも似たような箇所があるので、次回ご紹介します。
(99/08/08 99/08/09加筆)
まずは第1楽章から。冒頭はヴァイオリンからバスまでの総ユニゾンではじまります。ここではさすがに和音の補充というのはありえませんね。そのあとのソロの初めの音はなんとチェンバロだけでDの2オクターブ重ね(左手でオクターブ弾いている)。いかにも厚い響きです。弦も8フィートのチェロと16フィートのコントラバスで弾いていますが、これに匹敵するということでしょうか。19小節目からはいよいよ和音の補充がはじまります。

ここではカンタータ(そして恐らく原曲も)にはなかった内声部が加えられ、3〜4声になっています。とはいっても、独立した声部というよりは和音を弾いているという感じです。20小節目のスゴイ和音ですが、これがないカンタータでは、あっさりと過ぎ去ってしまうのですが、ここでは「どうだ!」という感じです。このあと25小節目に和音の補充がみられます。ちょっとしたことなのですがこれがあるとないとでは随分印象が違います。
続いては42小節から。

ここもカンタータでは2声で書かれていますが、チェンバロ協奏曲では左手でバスのほかにヴィオラパートを弾き、さらに、強拍では和音をならしています。これで、内声の響きが充実するわけです。
さて、このあと、典型的な和音補充の例、そして、バッハを弾く際のコツのひとつとも言うべき奏法、記譜法の例をご紹介しましょう。
ところで、この曲で鈴木秀美さんがチェロを担当しているCDがあるのをご存知でしょうか? ピエール・アンタイがソロを弾き、F.フェルナンデス、サントスなどがオケを弾くというCDです。ラ・プティット・バンドのクイケン兄弟がアンタイ兄弟に変わったような楽団ですね。ただ、16フィート(コントラバス)が中心の音作りをしているようで、あまり8フィートのチェロが聞こえないのが個人的には残念ですが。このCDにはフルート、ヴァイオリン、チェンバロのための協奏曲BWV1044も収録されていますが、そこにはRIPIENOのVNとして寺神戸亮さんも登場します。番号は「ASTREE E 8523」です。興味のある方は是非聴いてみてください。(きっとBCJブレーメン公演もこんな風な傾向のメンバー(寺神戸、バディアロフ、赤津、鈴木秀美他ヨーロッパ勢中心らしい)なんでしょうけど、音作りは全然違うんだろうな。ちなみに、ブレーメンでBWV1053ではなく、この曲を演奏するといううわさもある)。
(99/08/06)
いよいよ今回からは大本命の登場。
チェンバロ協奏曲第1番ニ短調BWV1052、この曲はバッハのあらゆる協奏曲の中でももっとも規模が大きく、かつ密度の濃い作品。力強く、充実感があり、いかにもバッハらしいという感じです。そして、原曲のヴァイオリン協奏曲からもっとも手の込んだ変更が行われました。このプロセスは、カンタータ第146番のシンフォニアにおけるオルガンパートと比較すると非常に良くわかります。
まず、特徴的なのが、右手の音域が比較的低めなこと。ヴァイオリンのための曲ではありますが、低い方の弦をより多く使うことと、重音奏法が特徴で、そのために、内声部がとても充実した響きだと言う印象を受けます。だいたい、第1楽章のテーマではE(ヴァイオリンの最も高い弦)より上の音は出てこないということからもわかると思います。E-DURのヴァイオリン協奏曲の華やかさとは対照的です。これがオルガン版ではさらに低い音域になっていて男性的です。チェンバロ協奏曲ではおそらくもとの音域に戻されたとは思いますが、それでもかなり音域が低いです。
この曲はヴァイオリン協奏曲が原曲なので、当然のことながらチェンバロソロパートは2声が基本です。確かにヴァイオリンの重音奏法はありますが、これはポリフォニックな扱いではなく、どちらかといえばホモフォニックな書き方をしているので、たとえ声部が多くなっても、基本的には2声と考えて問題ないと思います。実際にオルガン版を見ると、重音奏法で和音を弾いている所を除けば、完全に2声で書かれています。ところが、これがチェンバロ協奏曲になると、オルガン版にはなかった声部が新たに付け加えられています。ということで、見かけは3声になっています。そして、随所でかなり緻密な書法に書き改められています。その中で、明らかにオケの通奏低音楽器としての和声の響きを出すための音というのがかなりあります。これによって、オルガン版から音域を上げたことによる内声部の「空白」を埋め、響きがますます充実感を増す結果をもたらしたのだと思います。
ということで、バッハの最高傑作のひとつ、このチェンバロ協奏曲を見ていくことにしましょう。
(99/08/01)
和音だらけという印象があるのが、2本のリコーダーとチェンバロの協奏曲BWV1057の第1楽章です。この曲はブランデンブルク協奏曲第4番のヴァイオリンソロをチェンバロソロに置き換えたものですが、ヴァイオリンをそのまま弾いただけではあまりカッコ良くない。ヴァイオリンにとってはまさに高度な技巧を求められる場面でも、チェンバロだと実にあっさりと弾けてしまう。そんなことがあるせいかどうかは知りませんが、やたらと和音を「ジャンジャン」弾いています。通奏低音的であるといえばそうなのですが、でも何となく違うような気がします。そして、和音の響きが割合と高音域に達しているんですね。だから内声部を埋めるという感じではないです。純粋にソロが弾く和音といったらいいのでしょうか。もちろん、極めて通奏低音的なところもあります。原曲でソロヴァイオリンが休んでいる所がありますが、そういうところで和音を弾いている時には通奏低音的です。もっとも、演奏家もそういうところは敢えてバッハが書いた通りには演奏せず、自分流のリアリゼーションを使うことも少なからずあるようですが。
これだけ和音が書いてあるなら、ブランデンブルク協奏曲第4番の時にもこれを参考にしてリアリゼーションすればいいじゃないかと思われる方もいらっしゃると思います。でも、どう言うわけかそういう演奏にはお目にかかったことがない。やっぱりソロとして弾く和音と通奏低音として弾く和音は響きが違うのだろうし、それに、チェンバロ協奏曲の左手の方が原曲に比べてはるかに複雑だから、シンプルな原曲の時にはどうも合わないのかもしれない。私も個人的には余り趣味ではありません。
まあ、正直言って、私はこの曲については原曲の方がはるかに好きで、チェンバロ版には余り魅力を感じていないので、この辺でやめておきます。
(99/07/31)
次はチェンバロ協奏曲へ短調BWV1056の第1楽章です。これはヴァイオリン協奏曲(たぶんト短調)からの編曲といわれています。その第1楽章42小節以降です。ちょっと苦しいですが、これも原曲に和音を加えていることには違いなさそうなので紹介します。

この部分、ヴァイオリンなら左手に書いてあるFの音を(ト短調ならG)の音を一番低いG線で弾き、右手をA線で弾くことになるでしょう。このF(ト短調ならG線の開放弦)がヴァイオリンによってずっとなりつづけ、その下で通奏低音が動く。ヴァイオリン用ならこのFは8分音符ではなく16分音符で書かれるでしょう。ただし、開放弦でしかも弦が太いので、比較的長くあたかも8分音符のように響くのです。裏を返せば、ヴァイオリンでこのような音型が出てきたら、あたかもここに書かれているように響かせなければならないということです。
さて、通奏低音パートとヴァイオリンパートの間にある音ですが、これこそ和音の補充(否、内声の補充といった方が正確)ではないかと思われるのです。この和音の中で、Fはソロヴァイオリンパートの音でありながら、同時に通奏低音が弾く和音の一部にもなっていることに注意しなければなりません。ですから、上の楽譜の最初の8分音符のように音が2つしかなくても、ヴァイオリンパートとバスという風に単純に分けて考えるだけでなく、和音として弾くという意識も忘れてはなりません。それによって、おのずと弾き方も変わってきます。
これと似たような音型が、2台のチェンバロのための協奏曲ハ短調BWV1060第3楽章にも現れます。

この曲は、ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲が原曲といわれていますが、そのヴァイオリンパートにあたる第1チェンバロの右手を見てください。ヴァイオリン用なら普通はこう記譜するのです。細かくは楽譜に書いた通りですが、ここでも、この4声部をそれぞれ独立したパートとしてポリフォニックに処理するだけでなく、和声の変化も大切にしなければなりません。それを2台のチェンバロでどう弾くか。案外難しいかもしれません。
ちなみに、この2曲とも、ここで紹介した部分については、弦楽器が長い音符で和音を鳴らしていて、とても良く似ています。こういうところでは、通奏低音を担当する鍵盤楽器は、和音の頭にややアルペジオ風に和音を散らして弾くというのが一般的ではないでしょうか。そんなイメージがこれらチェンバロ協奏曲で和音を弾く場合にも合い通じるのでしょうか?
(99/07/24)
どの曲から取り上げようかと迷いますが、比較的わかりやすいものから。
ホ長調の協奏曲BWV1053の第1楽章のソロの最初の部分です。

左手を見てください。バス声部の上に和音が補充されているのがわかります。原曲ではこの部分がどうなっていたのかわかりません。内声部がオケの各パートに割り当てられていたのか、それともソロと通奏低音だけで、鍵盤楽器が和音を補充していたのか。カンタータ第169番でもここはオルガンだけになっていますので、多分原曲もそうだったのでしょう。そしてカンタータでは、オルガンの左手に「数字」がかかれています(でもアーノンクールのCDでは和音は補充されていません。そして、バスパートにファゴットを重ねて補強しています)。ただ、旧バッハ全集のスコアには「オブリガートオルガン及び通奏低音」と書いてあるので、「数字」はコンティヌオ用で、ソロは和音を補充しないという解釈もありえます。いずれにせよ、チェンバロ協奏曲のこの部分に、私は「バッハ自身によるリアリゼーション」を聴くことができるのです!
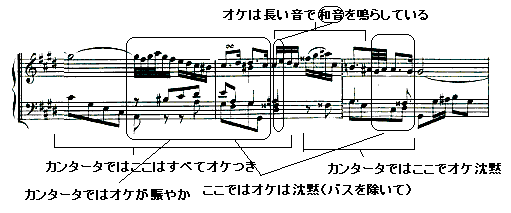
この部分も同じ様に「和音を補充」しているように見えますが、前のとはちょっと事情が違うようです。それは、チェンバロ協奏曲とカンタータのこの部分のオーケストレーションが大きく変わっているからです。バッハが和音を補充しているところでは、オケが沈黙している場合が多い。ここでもそうです。しかし、途中でひどい不協和音が出てくるところでは、チェンバロで和音を弾くだけではなく、弦の助けも借りてこの不協和音を強調しています。ところが、カンタータではそうはなっていない。チェンバロ協奏曲でオケが沈黙する前の方の部分では、逆にオケがフル編成(オーボエ属、ファゴットも加わって)で賑やかになっていて、一方で、不協和音はあまり意識できない。ソロを聞かなければ同じ場面だとはわからないほどです。チェンバロとオルガンの音量の違いから来ているのか、それとも、力点の置き方が変わったのか。いずれにせよ、オーケストレーションの変化がチェンバロの「内声部」にも影響を与えていることは間違いありません。良し悪しは別として。
この楽章にはあともう1箇所だけ同じ様な部分があるのですが、それについては省略します。
(99/07/20)
チェンバロ協奏曲における和音の補充の話をする前に、2つお話しておきたいことがあります。ひとつは現代の古楽器演奏における実践、もうひとつは楽譜についてです。
最初は、現代の古楽器演奏において、チェンバロ協奏曲の和音の補充がどのように行われているか。楽譜を見るというまでもなくチェンバロパートの左手と、チェロやコントラバス(ヴィオローネ)が弾くパートが、バスをになっています。チェロパートにソロのチェンバロとは別に鍵盤楽器などの和声楽器が加わったのかどうか、それはわかりません。イ長調の協奏曲BWV1055の楽譜を見ると、チェロパートにも和音をあらわす数字が書いてありますが(信憑性はともかく)、他の曲にはありません。これを見ると、別に鍵盤楽器が加わっていたようにも見えますが、一方、BWV1053の前のかたちであるカンタータ第169番のシンフォニアのオルガンパート(ソロパート)の左手にも数字が書いてあります。ということは、ソリストが同時に通奏低音奏者を兼ねていた可能性がある。では、現代の古楽器演奏ではこの問題にどう対処しているのでしょうか?
まず、ソロの他に通奏低音用として鍵盤楽器を使っているか。私の知っている限りでは、そういうのはありません。ではどうしているかというと、そこは人によって色々やり方が異なるようです。まずチェンバロ協奏曲の第1楽章や第3楽章の冒頭リトルネッロ。多くの曲では、ソロの右手と1ST VNはユニゾンですが、BWV1053の第3楽章、BWV1055の第1楽章、BWV1056の第1楽章では1ST VNから独立したパートになっています。BWV1052の第1楽章は全員がユニゾン。BWV1052を除いては、ユニゾンの場合に、そのまま1ST VNと同じ様に弾く人と、思い切って通奏低音として和音の補充に徹する人といます。独自のパートの場合でも、ずっと1ST VNと異なることを弾いているのではなく、途中からは1ST VNとユニゾンになる。そんな時には、ユニゾンになったらやはりそのまま弾くか和音の補充に専念するかで対応がわかれます。どちらかというと、独自の時には楽譜通りに弾くけど、ユニゾンになったら和音の補充に徹するという人の方が多いようです。やはり、冒頭は大編成ですから、しっかりした和音の支えがあった方がいいということでしょうか。とはいっても、前後のつながりとか、色々なことを考えて、その都度やり方を変えているというのが実態かもしれません。そして、ソロの部分も含めてそれ以外の箇所について、多くのチェンバリストは、楽譜に書かれた通りに弾いているようですが、レオンハルトなどは適当にあいている指で和音を補充しているようです。これはカンタータのシンフォニアの場合にも基本的には同じだと思います。もっとも、シンフォニアの右手は音域が低い(バスに近い)場合が多いので、和音を補充してしまうと旋律が聞こえにくくなってしまうおそれもあり、補充しても控えめにならざるを得ないでしょう。但し、BCJのように、常時二人のオルガニスト+場合によってはチェンバリストがいる場合には、もしかしたらソロは雅明さん、通奏低音は今井さんなんていうこともありうるかと思います。
次に楽譜ですが、現代発売されている楽譜というのは、様々なバージョン、つまり、バッハの自筆総譜、パート譜、弟子などの筆写譜、同時代人による筆写譜、後の時代(例えば息子の世代)の筆写譜、さらに、当時の出版譜などさまざまな資料の寄せ集めである場合が多いため、「原典版」といえども、どこまでバッハの意思を反映しているのかがわからないということに注意しなければなりません。自筆譜であっても、弟子や息子、さらにメンデルスゾーンの同時代人が「バッハ復興」の際に書き加えたものがあって、そこに書かれているのが、すべてバッハの意思だとは限らないのです。通奏低音パートの「数字」も例外ではありません。残念ながら、最初に述べたBWV1055の数字にしても、バッハが書いたものかどうか私にはわかりません。自筆総譜には何も書いていなくて、弟子による手稿パート譜に数字が書いてある場合に、スコアとして出版する際にその数字をどう扱うかその編集者のスタンスに任せられているところがあり、一般の読者にはどうもわかりにくいのですが、市販されている楽譜には、そこまでの情報は掲載されていないのです。同じ曲でも、出版社によってかかれている数字がまったく違うということもあります。ロ短調ミサもそうです。一番確実なのは、新バッハ全集の校訂記録と楽譜を照らし合わせ、さらに、自筆譜があればそれも見てみるというのがいいのでしょうが、なかなか難しい。ということで、一応、私の話の内容は今手許にある旧バッハ全集(これは当時の資料を割合と無批判になんでも受け入れてしまったらしい)を見た限りのことであるので、もしかしたら根本的な前提の間違いがあるかもしれないということを申し上げておきたいと思います。今年の10月には新バッハ全集のミニチュアスコアがベーレンライター社が出るそうですので、その時に誤りが見つかれば訂正したいと思います。
では、本題に入ります。
(99/07/18)
バッハのチェンバロ協奏曲の大部分が、他の旋律楽器、例えば、ヴァイオリン、オーボエ、オーボエ・ダ・モーレのための協奏曲からの編曲といわれていることは以前にお話した通りですが、ということは、もともとソロは単旋律であったということ。ヴァイオリン協奏曲のように重音奏法を駆使して多声部のソロパートを書くこともありますが、それは例外的。チェンバロ協奏曲に編曲する時には、基本的には原曲のソロパートをチェンバロの右手に、バスパートを左手に(これも例外がありますが)あてがいます。つまり、チェンバロ協奏曲のソロパートは基本的には2声で書かれているといってもいいでしょう。ところが、実際に楽譜を見てみると、必ずしも2声ではない。ところによっては4声のこともあります。この付加された声部というのは一体何なのでしょう?
さて、チェンバロの左手ですが、これは原曲では当然のことながら通奏低音パートを担当。左手でバスパートを弾き、右手で和音を補充していたわけです。ところが、チェンバロ協奏曲になると、右手はもともとのソロパートに割り当てられてしまうので、和音の補充をする手がなくなってしまいます。いくら、弦楽器が和音を弾いているからといって、鍵盤楽器で和音を補充しないということはあるのでしょうか? ひょっとしたら、あいている指で、和音を補充していたのかもしれないし、何もしなかったのかもしれない。それとも、もう一台鍵盤楽器があって、それが通奏低音パートを担当していたのでしょうか? これは、バッハのチェンバロ協奏曲に限らず、ヘンデルのオルガン協奏曲でなどでも大いに問題になります。
バッハは、当時当たり前だったような記譜の省略をあまりせずに、比較的弾いてほしい通りに楽譜を書いたといわれています。他の作曲家なら数字付低音(これは明らかに略記法)で済ませてしまうところを、きちんと和音を音符として書いています。オブリガートチェンバロと旋律楽器のためのソナタなどみても、そのことがよくわかります。ということは、チェンバロ協奏曲でも和音を補充すべきところにはちゃんと音符を書いていてくれるかもしれない。そうやって楽譜を見ると、あった! ということで、バッハが補充した和音とチェンバロ協奏曲における通奏低音について、しばらく考えてみようと思います。
 話しは横道にそれますが、チェンバロ独奏曲なのに、低音部に和音を示す数字が書かれているという珍しい曲があります。有名な「最愛の兄の旅立ちに捧げるカプリッチョ」BWV992の第3曲がそうです。楽譜を見ていただければわかるかと思いますが、右手が休符になっていて、左手(バス)に和音をあらわす数字が書いてあります。98年度山梨古楽コンクールの課題曲の中にこの曲があったようで、関根敏子さんの感想が古楽情報誌アントレ99.6月号に掲載されていますが、その中で、この部分の奏法が奏者によって大きく異なっていたことに言及されていました。中には、まったく和音を弾かなかった人もいるようですが、果たして、バッハはどのような奏法を望んでいたのでしょうか?ちなみに、この楽譜は自筆譜ではなく筆写譜なようです。
話しは横道にそれますが、チェンバロ独奏曲なのに、低音部に和音を示す数字が書かれているという珍しい曲があります。有名な「最愛の兄の旅立ちに捧げるカプリッチョ」BWV992の第3曲がそうです。楽譜を見ていただければわかるかと思いますが、右手が休符になっていて、左手(バス)に和音をあらわす数字が書いてあります。98年度山梨古楽コンクールの課題曲の中にこの曲があったようで、関根敏子さんの感想が古楽情報誌アントレ99.6月号に掲載されていますが、その中で、この部分の奏法が奏者によって大きく異なっていたことに言及されていました。中には、まったく和音を弾かなかった人もいるようですが、果たして、バッハはどのような奏法を望んでいたのでしょうか?ちなみに、この楽譜は自筆譜ではなく筆写譜なようです。
(99/07/17)